「がんもどき」理論を検証する (3)
昨日のニュースですが、理化学研究所が蛍光イメージング技術による細胞周期のリアルタイム解析を開発し、その結果、抗がん剤の濃度によって細胞周期が変化することを発見したと発表しました。
今回、抗がん剤に対する細胞の応答性を調べる研究にFucci技術を活用し、個々の細胞が見せる反応を定量的に観察することを試みました。古典的な抗がん剤として有名なetoposide(エトポシド)で処理した細胞の反応を経時的に調べたところ、低濃度ではG2(分裂前準備期)期における細胞周期進行が停止する現象(G2 arrest)、中濃度では細胞核が分断化する現象(nuclear mis-segregation)、また高濃度では細胞分裂をスキップして核DNA量が増大する現象(endoreplication)が観察されました。nuclear mis-segregationを示す細胞が死に向かうのに対して、endoreplicationを示す細胞は、抗がん剤に対する抵抗性を獲得したものと見みなされます。この結果は、高濃度の抗がん剤投与によってがん細胞がより悪性化する可能性を示しており、現行の抗がん剤開発におけるスクリーニング方法に一石を投じるものと注目されます。
これは、高橋豊氏や梅澤医師が提唱する「休眠療法:低用量抗がん剤治療法」の有効性を示唆するとともに、「がんもどき」理論の根拠となっている”がん細胞分裂周期一定説”を否定するものです。がん細胞は本当にしたたかです。単純な推論や線形思考では太刀打ちできないと思います。
私は、心情的には近藤氏の主張に多いに惹かれます。現状の常識を敢えてひっくり返そうとするその反逆精神は賞賛したいという気持ちがあります。統計データの見方・考え方も参考になります。万年講師という逆境にもひるまず、自らの主張を堂々と貫き通すという一貫性は尊敬に値すると思っています。
ただ、現実にがんを持っている一人のがん患者としては、近藤氏の理論を自らの治療に適用しようとしても戸惑うばかりです。近藤氏の言い方はセンセーショナルな書き方になっていますが、それを捨象して本質だけを抜き出せば、案外と常識的な主張にすぎないと思います。
「抗がん剤は効かない」にしても、「効く」とはどういうことを指しているのかにもよりますが、固形がんが抗がん剤で治ることはないというのは、一部の例外はあるにしても共通認識でしょう。延命効果はあってもごくわずかであり、これもほぼ共通認識です。膵臓がんに対するタルセバの延命効果は10日程度ですが、これを価値があるとするか無価値とするかは、患者の置かれた立場や価値観によって異なるでしょう。幼い子供を抱えた患者であれば少しでも長生きしたいと考えるのは当然ですが、80歳、90歳なら「止めておこうか」となるかもしれません。「むだな治療はするな」という近藤氏の主張は、「むだ」かどうかは患者の価値観によって決まるとするならば、あたりまえすぎる主張だとも言えます。
「5年生存率が70%のがんなら、70%はかんもどきで、30%は本物のがんと考えて良い」と近藤氏は言います。そして、本物のがんならいずれ宿主を死に至らしめるから治療はむだであり、がんもどきなら放っておいても転移しないから、こちらも治療の必要はないと主張します。その根拠が単に一つの仮説に基づくものであり、単純な線形思考だと説明しました。また、がんの性質は遺伝子によって決まっているとの主張にも根拠がありません。がん細胞が大きく育つには10年、20年と時間がかかりますが、その間に転移能力を獲得した細胞が生き残って増大するのです。がん細胞の世界でも適者生存の競争があり、より環境に適した細胞が生き残って増えていくのです。その過程で転移に必要な遺伝子変異を獲得し、あるいは遺伝子が発現する能力を獲得するという説が有力です。
近藤氏の考えは、1個のがん細胞ができた時点で宿主の運命も決まっているという、とんでもない運命論、遺伝子万能論です。一つ一つは決定論的な現象であるにもかかわらず、あまりにも多くの因子がお互いに影響を与えながら系全体の行動に作用することによって、全体としては予測のつかない、混沌とした状態に見える系を”複雑系”と呼びます。人間もがんも、もちろん複雑系です。がん細胞一つ一つは遺伝子によって決定論的に振る舞うにしても、全体は相互に関連して予測不可能な複雑系として動作するのです。
また、複雑系においては「特別な現象が起きるために、特別な理由は必要としない」という性質もあります。「がんと自己組織化臨界現象」ではそのことを紹介しました。特別な原因がなくてもがんが消失する”自然退縮”は起こり得るのです。また、複雑系では初期条件のわずかな違いが、その後の運動をまったく異なるものにします。だから予測不可能なのです。代替療法には効果があると証明されたものは一つとしてない、しかし全てを無視するのは勿体ない、とシュレベールが『がんに効く生活』で言うのは、このことを指しているのです。
がん患者はみんな治りたいのです。統計データの右側、いわゆる「ロングテール」に自分もなりたい。そして誰にもその可能性があるのですから、近藤氏のように運命だと諦める必要はないのです。
2006年の夏に膵臓がんで余命3ヶ月と言われたふうきさんのブログがあります。病院からも追い出されて腹水がたまった状態で自宅でただ寝ているだけで、その年末を過ごしたそうです。しかし今も抗がん剤を投与しながら頑張っています。本人も医者も驚いて「奇跡」だといいますが、こんなことだって複雑系だからこそ起きるのです。Ⅳ期のがんが自然退縮するという特別なことだって起きてもよいのです。ガンの患者学研究所の専売特許ではない。しかし一方で、運悪く抗がん剤の副作用で亡くなった方はブログを書き続けることができないので、当然ながら我々の目に触れることはありません。
未来は予測できません。分かるのはただ全体としての傾向だけです。抗がん剤を使った99人のデータと無治療の99人のデータがあったとして、ある患者が抗がん剤で50人目に位置したとしても、無治療の場合も50人目であったかどうかはわかりません。それより良かったかも知れないし、悪かったかもしれない。一人の患者が両方を経験することができないのですから、あたりまえです。自分の場合どこに位置するかは分からないし、余命が延びたかどうかも実感できません。
がんに限ることではなく、人生の全ての局面で言えることですが、結局は限られた情報しかないときの意志決定はどのようにするのが合理的であるか、という問題に帰着します。
未来が予測できないならば、自分の価値観・人生観に従って決めるしかない。やってみなければ分からないことを事前にあれこれと悩むことは無益でしょう。ある程度の成功の確率が理解できたら、あとは”直感”で決めればよいのです。
以前に「冒険の旅の物語」として次のようなことを書きました。
任務は達成できることもあれば、失敗することもある。いつも必ず達成できるわけではない。この物語の核心は、「最終的に主人公が変容している」ということである。さまざまな体験によって鍛えられ、最初の青二才ではなくなっている。任務が達成できたのは、冒険によって身につけた新しい知恵と能力を使ったおかげであり、任務が達成できなかったとしたら、最初の野望はばかげた気まぐれであり妄想であったということである。彼の人生を真に満たすものは最初に考えていたものとはまったく違うということに気付くのである。
がんとの闘いの旅においても、主人公である私たちはその旅を楽しむことができるし、その過程で成長することができる。ただ単に「がんとの闘いだけに捧げた人生」ではなくなっている。死と闘うことの愚かしさを知るようになる。
道元はかく言う。「生というときには、
生よりほかにものなく滅というときは、滅のほかにものなし。かるがゆゑに、生きたらば、
ただこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべし。いとうことなかれ、ねがふことなかれ。」 良寛はかく言う。「災難に逢う時節には、災難に逢うがよく候。 死ぬ時節には、死ぬがよく候。 是ハこれ災難をのがるる妙法にて候」
おわり



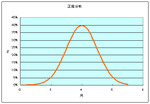






sho先生。コメントありがとうございます。
近藤氏への反論、参考になります。こんな専門家からの反論が知りたかったのですよね。ただ、リンクされた図の「打ち切り例」が多いのは気になります。
タルセバの10日程度の延命というのは生存期間中央値付近がたまたまその程度しかジェムザール単独と差がありませんでしたが、生存曲線全体ではしっかり差が出ています。
近藤誠氏の文芸春秋2月号の記事批判を行っています。ご参照ください。
近藤氏「抗がん剤は効かない」への反論II-④近藤氏のデマ
http://ameblo.jp/miyazakigkkb/entry-10780021777.html