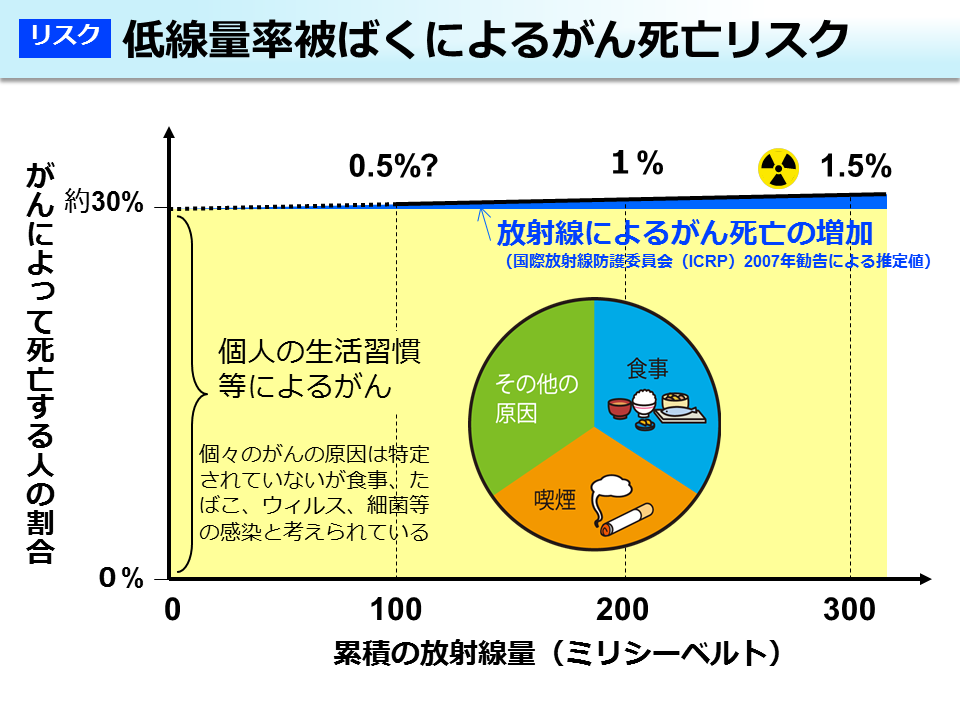セカンドオピニオン拒否され、適切な治療受けられずー膵臓がん患者が提訴
ーー 目次 --

先日8月30日に、膵臓がん患者さんが、独立行政法人国立病院機構 静岡医療センターと元の主治医(O医師)を東京地方裁判所に損害賠償の提訴し、その記者会見が厚生労働省記者会で開かれました。
膵臓の腫瘍が見つかりIPMNの疑いがあったにもかかわらず、その事実を知らせなかった。腫瘍マーカーも基準値を超えていたのに、患者に説明することもなく、説明責任も適切な治療をすることなく放置し、その結果悪性の膵癌に進行し、腹膜播種が生じるまでに到った、というものです。
記者会見には、新聞記者、ジャーナリストなど14名の方が参加されました。
静岡新聞と読売新聞静岡版に記事が載っています。

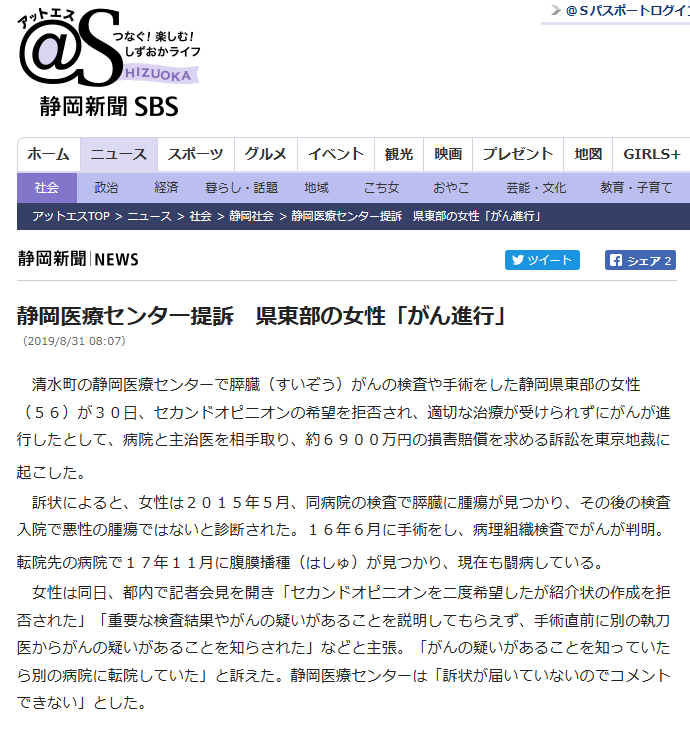
記事だけでは詳細な経過や、原告の訴訟意図が分からないと思いますので、記者会見の席で配付された資料「原告の思い」を、原告の承諾を得て掲載します。(一部改変。中見出しは私が付けました)
事実とすれば、患者の命よりも病院の経営や評判を優先するという、同じ膵臓がん患者としても許せない行為です。
原告の思い
2019年8月30日
がんとは知らされなかった
静岡医療センターでの初診から手術に至るまでの診療のなかで、元の主治医(O医師)からは「が んの疑い」という言葉を一度も聞くことはありませんでした。
セカンドオピニオンの希望を拒否されたときの理由は「がんではないので紹介状は書 けない」というものでしたし、細胞診のあとの見解でも「ここまで腫瘍が大 きくなっていて、まだがんになっていないので将来的にがんになる可能性はほとんどな い」という話でした。
また、手術をすることになった時にも、O医師からは「腫瘍が大きくなってきて、 中で爆ぜると危険なので切ったほうがいい。前にもそのような患者がいたので」という 話だけで、「癌の疑い」や、将来がん化する可能性やそのリスクなどについてなど、全く知らされませんでした。
執刀医から初めてがんだと知らされる
ところが、手術日程が決まり、執刀医の医師とのIC の時に、開口一番、執刀医から「がんの疑いがあることは聞いていますね」と言われ、もう、頭が真っ白になっ たと言うか、そのときは現実を受け入れられない気持ちで、数日後に迫っている手術日 まで十分な熟慮期間をとることができないまま、手術することになりました。
そして、術後の病理検査の結果、膵臓がんのステージⅢ (新しい区分法では、一部リ ンパ節に転移がみられるステージ ⅡB)だと聞いたのも、O医師からでは なく、執刀医からで、結局、O医師の口からは、最後まで、一度も「がん」 や「悪性」という言葉はありませんでした。
それらの一連の流れがとても不自然で、不可解に感じ、一体、診療の中で何が起こっ ていたのかを知りたくて、カルテの証拠保全の手続きを弁護士の先生方にお願いしまし た。
基準値を超えた腫瘍マーカーの結果も教えず
そして、カルテからは、私が知らされていなかった事実が、たくさん見つかる事にな りました。
まず最初にわかったのは、2015 年の検査入院の際に、腫瘍マーカー値を検査してい たことです。
この腫瘍マーカーについては、静岡がんセンターにセカンドオピニオンを受けさせて 欲しいと申し出た際、O医師からは「まだ検査の途中だし、検査途中で紹介状など書 いたら私が笑われる、それに、がんときまったわけではないのでがんセンターに紹介状は書けない」と言われ、諦めざるを得ない状況になったときに、「それではマーカーの検査をして欲しいです」と頼んだのです。
しかしO医師からは「初期段階でマーカー検査しても意味がない」と断られたという経緯があったので、カルテにマーカーの検査結果を見たときは本当に目を疑いました。
そして、さらに驚いたのは(マーカーは 2015年の6月と7月と2カ月に渡って検査した記録があったのですが)基準値を大幅に上回る、その数値でした。
膵臓の腫瘍マーカーであるCA19-9や Dupan-2が基準値を遥かに上回っていたのを見て、なぜ、これを検査した時に教えてもらえなかったのか、この数値さえ教えてもらっていれば、O医師がいくら「がんの疑いはほとんどない」と言ったところで、病院を逃げ出してでも、がんセンターに駆け込んだと思います。
この後も、カルテを精査する中で判明していく数々の事は、私が知らされていなかった事実で、そのたくさんの「真実」を前に、私には本当に辛い思いの連続でした。
入院時にはIPMNの疑い、しかし患者には告げず
次にショックだったのは、私の腫瘍は2015 年の検査入院当初にIPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)を疑うべき段階で、腫瘍の大きさは3センチを超えていました。そして、先程お話したようにその頃のマーカー値も高い値だったわけですが、IPMN のガイドラインに、IPMNは、将来がん化する可能性がある腫瘍で、3センチ以上の場合は「悪性が疑われる」ため、「強く手術を考慮」という記載があることを、あとで知り、とても衝撃を受けました。
2015年6月当時、すでにマーカー値も高値だったわけですから、IPMN ガイドラインに沿って、その時点で手術する必要があったと私は思っています。
IPMN は、たとえ癌化しても膵臓内におさまっている状態のときに切除できれば予後の良い腫瘍だと知りました。
しかし、一旦膵臓外に浸潤などがあった場合は、一般の膵臓がんと同じ経緯をたどるのだそうです。
1年後に手術するもステージⅢの膵癌が確定
私が手術したのは、初診で膵臓に腫瘍が見つかってから1年経ったあとでした。
参考までに、手術で切除した臓器は、膵臓尾部(事前の説明では3分の1でしたが、約半分)と脾臓、胃の一部と胃の血管(5本のうち2本)、さらに副腎です。
これらをみても、初期の段階では膵臓内に収まっていた腫瘍細胞が進行し、他の臓器にまで浸潤してしまったため、たくさんの臓器を切除しなければならなくなったことが分かると思います。
最初に腫瘍が見つかってから手術に至るまで、適切な検査などしていただくこともなく、1年が経過し、手術となり、結果、難治性の膵臓がんが「確定」しました。
さらには、その手術の経緯についても、病院が手術をした方がいいと決めたのが検査入院の翌年の2016年の3月下旬頃でしたが、その時に撮った CT と、6月の手術直前に撮ったCT とを比較しても、病状は進行してしまっていました。
膵臓がんのような進行の早い癌腫は、がん専門病院であればできる限り迅速に対応するそうです。現に、がん研有明病院などでは、膵臓がんは他の癌腫の手術とは別枠で予定が組まれているとも聞いています。
二度にわたるセカンドオピニオン拒否
もし手術が決まった段階で「がんの疑いがある」事さえ聞かされていたら、すぐにでも静岡がんセンターに転院の希望を出していたと思います。
実は以前から、医療センターのO医師には「もしだった場合はがんセンターに転院したい」と言うことを話していました。
静岡がんセンターには、肝胆膵外科で権威の上坂先生が居られることを知っていたからです。
医療センターで、セカンドオピニオンを拒まれただけでなく、要所要所で発生していた重大な事実を「全く」教えて貰っておらず、前癌状態だったIPMN が進行して他臓器に浸潤し、癌化するまでに至りました。
正しい情報を教えてもらうことができなかった事で、私は、手術に至るまで、一度も、自分自身が望んだ納得できる治療を受けることができませんでした。
マーカー値のように、分かりやすい数字に表れている事ですら、教えてもらっておらず、なぜこのようなことになっていたのか、事実を知れば知るほど、本当に理解に苦しみました。
日々の闘病生活のなかでは、腹膜に転移が見つかり、膵臓がんの腹膜播種は抗がん剤が効きにくく、有効な治療法もないという中で、闘病を続けているという現実があります。
がんの闘病は、それだけでも身体的にも精神的にも、つらいことが多いです。
そのうえ、一方では、カルテからは知らされていなかった数々の事実を知ることになって、「あのとき、セカンドオピニオンの紹介状さえ書いてもらっていたら…」「マーカ一値さえ教えて貰っていたら.…」という思いが、常に私を苦しめました。
私は今の医学の力では助からない状態と言われています。
私は、なぜ、死んでいかないといけないのでしょうか。
なぜ、セカンドオピニオンの希望を拒否され、マーカー値の結果を教えて貰えず、がんの疑いがあることも手術直前まで知らされず、医療センターで手術することになってしまったのでしょうか。
被害者は原告だけではなかった!
今年の春ごろになって、私と同じ膵臓がん患者のかたが、静岡医療センターの同じ医師に、セカンドオピニオンを希望しても聞いてもらえず、転院をお願いしてもなかなか動いてもらえず、手術できるかどうかギリギリのところだった状況が、満足な治療を受けることもなく漫然と転院のタイミングを引き伸ばされ、その間に癌が進行して、手術出来ない状況になってしまい、その後、亡くなられた患者さんがいることを知りました。
その方は、やっと静岡がんセンターに転院したときに医師から「なぜもっと早く来なかったのですか」と言われたのだそうです。
そもそも、全癌腫の中で、膵臓がん患者数は、決して多くないのです。静岡医療センターではさらに数が少ないであろう膵臓がん患者さんが、私と同じような被害に遭われたと知った時は、本当にとてもショックでした!
わたしがカルテから知った数々の理不尽なことが、自分だけのことではないのかも知れないということを感じ、とても衝撃を受けました!
私は早期手術をしていたら生き延びられたのに、それをしてもらえませんでした。
もしO医師が「症状がよく分からなかった」というのなら、私はセカンドオピニオンを希望していたのですから、少しでも早く紹介状を書いて転院を促すのが本来の医師の務めではなかったのでしょうか?
また、手術に至るまでの期間に何度か外来でO医師の診察を受けていましたので、マーカー値や正しい情報を私に伝える機会はあったはずでした。
でも、O医師は最後までそれをしませんでした。
一体、なぜなのでしょうか?
私と同じような被害に遭った患者さんがいたことを知ってからは、私は、
「何らかの理由で、故意に放置された」
と考える方が自然ではないか、と感じるようになりました。
病院の診療実績を優先したのか?
静岡医療センターが、あるいはO医師個人が、何らかの理由で、診療実績を増やしたい、他の病院に患者をとられたくないという意図があったのではないかと、感じるようになりました。
静岡医療センターは、静岡県の「地域がん診療連携推進病院」に指定されています。
ちなみに、国の指定である、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要があるそうです。例えば「がん患者登録数」であったり「がんの手術数」であったり、というものです。
たとえば、ある病院で手術したり、癌と診断が出ると、その病院の「がん手術数」や「がん登録数」として、カウントされます。
静岡医療センターは県が認定した「地域がん診療連携推進病院」であるわけですが、私は静岡医療センターで手術をし、がんの確定診断を受けましたので、私としては本当に不本意ですが、静岡医療センターの「がん登録数」と「がん手術数」にカウントされています。
そして静岡医療センターの「地域がん診療連携推進病院」としての評価の一部になっている、そのことは事実です。
病院の認定の判断に、病院の不適切な行為でカウントされた患者の数が含まれていて、良いものなのしょうか?
O医師から、ほかの患者さんも同じようにセカンドオピニオンや転院を速やかに対 応してもらえなかった事を考えてみて、私の案件の他には「ない」と言いきれるのでしょうか。
その件について、私は、厚生労働省や、静岡県に対して問題提起をしたいと思います。
同じ被害者を増やさないためにも
最後に、、
今の私は、今の医療技術では殆ど助かる見込みはないと言われています。 現在、私の病状は「月単位」で考えており、いつ急変するかも分からない状況の中で生きています。
私は、私の残りの大切な命の時間を、この裁判に費やす覚悟をしました。
これから先、私と同じような被害に遭われる患者さんが出ないことを願い、また、過 去に病院から理不尽な対応を受け泣き寝入りしてきた患者さんの気持ちも背負って、裁判上で、闘うことにしました。
ですから、少しでも長く生きて、 最後まで裁判を見届けたいです。。
私からの思いは、以上です。 ありがとうございました。