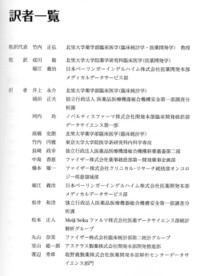今日の一冊(39)『鹿の王』
上橋菜穂子の新作『鹿の王』は、異世界を舞台にした謎の病を追う医療サスペンスであり、異文化との交流を正と負の側面から描く物語である。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”B0741T2P8T” title=”鹿の王【全4冊 合本版】 (角川文庫)”]
病とは何か、免疫とは何かが、人はなぜ死ぬのかが、物語の通奏低音になっている。著者はインタビューに次のように答えている。
「命は誕生した時から終わるように設計されているのだろう」という発想は、かなり前から持っていました。すべての病や事故を回避できたとしても、最終的には老衰になるわけですが、がんが老化現象だというのは言い得て妙で、人がもし事故に遭わず、あるいは脳血管疾患にもならず、心臓疾患にもならず、感染症をも生き延びても、自分の細胞が暴走してがんが発症する確率が高い。となると、たとえ偶然のミスの積み重ねが原因だとしても、がんもそれによる死も生体がもともと持ってしまっているシステム上の必然だと言ってもよいような気がして。
あとがきに書かれているように、サケが産卵後、極端に免疫力が低下して病を発症して死んでいくとの記述など、柳澤桂子の『われわれはなぜ死ぬのか―死の生命科学』から多くの示唆を得ている。
彼女の著作は、このブログでも何度か紹介している。(がん患者が考える生と死(1)「生きて死ぬ智慧」)そこで次のように書いた。
「性=生」が生じたことにより「死」は必然的に現われるようになった。われわれの感覚では、生きているものが死ぬのであるが、生物学的に見れば、死ぬことによって、そうした戦略をとることによって種の繁栄が確実になるのであるから、「死ぬから生きることができる」のである。ひとつの個体が永遠の命を持たないことによって、種としての生が保証されるのである。
なぜ死ななければならないのか、なぜ「この俺」ががんなのか。がん患者にとって「死」は常に切実なテーマである。田沼靖一は『遺伝子の夢―死の意味を問う生物学 』で、「ヒトは、進化の過程で可老可死を選択することで生き残ることができた生物の末裔なのです」と言う。柳澤桂子は「私たちは、死を運命づけられてこの世に生まれてきた。しかし、その死を刑罰として受けとめるのではなく、永遠の解放として、安らぎの訪れとして受け入れる ことができるはずである」と。
しかし、弱者が常に虐げられ抹殺される世において、「死」に抗うこともまた「生きる」ということである。『鹿の王』で主人公は語っている。
(病に命を奪われることを、あきらめてよいのは)
あきらめて受け入れる他に、為すすべのない者だけだ。
他者の命が奪われることを見過ごしてよいのは、助けるすべを持たぬ者だけだ。