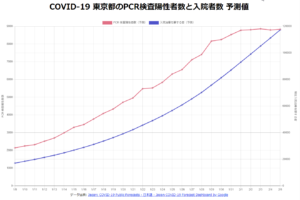今日の一冊(149)『名僧たちは自らの死をどう受け入れたのか』

死はやってくる
「死は受入れられない」。
釈迦が説く生老病死から人間は決して免れることができないのだから、たとえ悟りをひらいた名僧、高僧だって死は恐怖であるはずだ。
しかし、死はやってくる。受入れたくなくても受入れざるを得ない。
治らないがん患者にとっては、名僧、高僧のような悟りの心境に達するには時間もない。まさかがんの告知と同時に修行をはじめるわけにもいかない。
親鸞、一休、良寛、西行、空海、一遍、最澄、それに鉄舟と山頭火。彼らが迷い悩みながら辿り着いた人生の終い方とは。
臨済宗の高僧 仙厓は、死の間際に「死にとうない」と呟いたそうな。生の中に死があり、死のなかに生があり、両者はひとつと説く臨済宗である。弟子たちはおろおろしたに違いない。
一度地獄を見た者の生き方には二通りある。「生」にすがりつくか、助かったいのちは余生として開き直るか。
「生」にすがりつけば、二度と地獄に落ちまいと必死の努力をする。だが、眼下の地獄を見すえるこの生き方は、常に地獄の影がつきまとうため、心の平静は得られまい。開き直ったものは眼下の地獄に目もくれない。失うものはないと腹をくくれば、恐いものはない。
僧籍を剥奪された親鸞は、己の運命に絶望もせず、わが身の不幸を嘆くこともせず、逆境を受入れ肯定し、現状に身を投じていく。
逆境に対して「今に見ておれ」と踏み台にする生き方は、「今ある自分」を否定することである。親鸞にとって死を受入れるとは、臨終の瞬間まで「今を生ききる」ことであった。
「人生は借用書」返す期限が来たら返せば良い、ただそれだけのこと
「人生は借用書」と喝破した一休。
自分の生きてきた人生そのものが形見だと遺した良寛。出家することで悟りをひらきたいと思うその心が「執着」であり、それすらも捨てよという西行。「明日」を捨てよ、捨てて捨てて、その果てに平静があるとする一遍。
「明日」のことを考え、何かを「獲得」しようとするから悩みが生じるのである。
生も死も、地位もお金も思い通りにならないのがあたりまえ。親も子も、伴侶も思い通りにはならない。自分の身体でさえ同じこと。コントロールできないことをコントロールしようとするから悩みが生じる。
現代医学には限界がある。治るものなら治す努力をすれば良い。治らない病まで治そうとするから迷いが生じて、オタオタする。
希望を持つのは良い。しかし、いつしか「希望」が「執着」になってしまう。治そうと「執着」している患者がいかに多いことか。
一遍はこう言う。「死ぬときは死ぬがな。それまでは生きているがな」そして、「明日」への思いを捨てさえすれば、すべては捨てられる、と。
捨てれば、身軽になって、「ただ今のこの日」に命を集中して生きられる。
この身体は借り物。借用書には「必ず返すべし」とは書かれているが、「いつ返せ」とは書かれていない。返す期限は誰にも分からない。身体もがんも「複雑系」だから、原理的に「未来は予測できない」。それを予測しようとするから要らぬ悩みが生じる。
返す期限が来たら返せば良い、ただそれだけのこと。