今日の一冊(157) 『ドキュメント がん治療選択』金田信一郎
「日経ビジネス」記者・ニューヨーク特派員、日本経済新聞編集委員を経て2019年に独立したジャーナリストの金田信一郎氏が、食道がんステージ3を告知されてから、手術を土壇場で拒否し、放射線治療と抗がん剤治療に行き着くまでの迷いながらの選択を詳細に記録した一冊。
ジャーナリストの性でしょうか、同じ病室の患者のことなども詳しく書かれていて、いつもメモを取っていた様子が伺えます。それだけに、432ページという分厚い本に仕上げっています。

2020年3月、突然ステージ3の食道がんに襲われた。友人からは「患者にできるのは病院と医者を選ぶことだけ」ともいわれるが、紹介された東京大学医学部附属病院(東大病院)に入院し、癌手術の第一人者で病院長が主治医になった。母親の癌も治療してくれた医者であったので任せることにしたが、病状を詳しく説明してくれない。インフォームドコンセントのかけらもない。
曖昧な治療方針に違和感を拭えず、セカンドオピニオンを求めて転院。しかし転院先でも土壇場で手術をせず放射線による治療を選択し、今では以前とほぼ同じ日常を取り戻した。
本の中の気になる箇所
日本人の2人に1人が罹患する「がん」。長生きするほどがんと宣告される可能性は高くなり、男性における死亡率は26.7%に達する。それでも、がんになった時、自分に合った病院や治療を選択できる人はほとんどいない。
欧米に比べて、日本のがん治療では手術比率が圧倒的に多く、放射線治療の割合か少なくなっている。欧米では「手術から放射線治療(SBRT)へ」という流れが顕著である。
日本の放射線治療が、欧米諸国に比べて劣っているわけではない。「もっと放射線治療のメリットを広めていかないと、『癌は切除するもの』が常識となって、本来、放射線を受けたかった人が手術に回されていく」と、大船中央病院放射線治療センター長(放射線医師)の武田篤也は述べている。
なぜ、日本だけが手術に偏った治療を続けているのか。
かつて日本の医療現場は、医師の裁量と自由度が高い「聖域」とされていた。診療所や開業医を中心に医療が展開され、彼らを中核に据えた日本医師会が強い政治的発言力を持つ時代が続いた。
だが、1990年を境にして様相が一変する。それまでの経済成長期には医療費の上昇をGDPの成長が覆い隠していたが、バブル崩壊で経済が停滞するなかで、医療費だけが膨らみ続けた。1990年に国民医療費のGDP比は4.6%だったが、2000年には約6%、2011年には8%近くまで上昇する。
この時期、開業医比率が大きく減少し、抵抗力を失っていくなか、データによって成果が高いとされる治療に絞り込む、「標準化」の波が襲ってくる。
既に欧米では、1990年代初頭から「エビデンス革命」が吹き荒れていた。1991年、カナダの医師ゴードン・ガイヤットが「エビデンスに基づく医療(EBM)」を提唱。続いて第一人者のカナダの医師デービッド・サケットが論文(「エビデンスに基づく医療 それは何であり、何でないのか」)を発表し、世界に広まっていく。
経験知による医療の死角を克服するためにも、臨床試験等による結果(エビデンス)を重視して治療法を決める──。その方法論は、医療費の肥大化に悩む日本にも到来する。
2000年代、日本ではエビデンスを基にした「標準治療」を確立する動きが加速する。06年には「がん医療の均てん化(全国どこでも癌の標準的な専門医療を受けられるよう、医療技術等の格差の是正を図ること)」を謳ったがん対策基本法が成立。実績が高い治療法を示した「診療ガイドライン」がネット上で公開され、全国の医療現場に広まっていった。
そこに日本独特の、全国で一本化された診療報酬制度が「総額の上限」として機能し、医療費の抑制に成功する。2011年以降も、国民医療費はGDP比8%以下の水準で推移している。
その決定システムには、政官業の微妙な力学が働いている。まず、官(財務省)が医療費の引き下げを要請するが、一方で業(医療界)が引き上げの必要性を訴える。すると、官(厚生労働省)が調整し、政(内閣)が妥結策を最終決定する。この政官業のトライアングルがバランスを取り、医療費を一定の比率に保つ。
だが、この決定過程には、医療の中心にいるはずの患者の視点が欠落している。そして、一見すると均衡しているかに見える医療は、「患者不在」のまま、その中身が大きな変化を遂げることになる。
EBMの行き着いた先が、マクドナルド化
エビデンスという、臨床での数値結果に裏打ちされた「標準治療」に従う–その結果
「かつて、治療を自由に考えてきた医師が、『マニュアルどおりの治療さえしておけばいい』と考えるようになってしまった。目の前の患者ごとに治療や薬への反応が違うのに」
がん研究会・がんプレシジョン医療研究センター所長(外科医)の中村祐輔は、危機感を募らせている。そして、こう表現する。
「医療のファストフード化」
20世紀の大量消費社会を象徴する産業の仕組みに酷似しているという。客(患者)の意向や要望には応じず、画一的な調理(治療)を効率的に進めていく。
「標準治療が見つかる場合は対応できるが、マニュアルにない病状の患者を見た途端に、医師はお手上げになってしまう」
当然の帰結として、医師と患者との間に、深い溝ができていく。
浜松オンコロジーセンター院長で内科全般や癌治療に当たる渡辺亨は、地域住民の治療や医療相談を受ける傍ら、医療情報サイトを開設して多くの癌患者や家族と交流してきた。そして、こう警鐘を鳴らす。
「患者の間に、医者に対する不満が渦巻いている。その原因は、医師のコミュニケーション能力の低下にある。患者がどんな医療を求めているのか、一緒に話し合って決めることができない」
標準治療が最高とは限らないが・・・
上の本は「標準治療こそが最高のがん治療」であると謳っている。怪しげた代替療法と比べたときには、そうした面もあり、間違いとは言い切れない。
しかし、実際の現場では手術ができなければ抗がん剤、別の治療法の選択肢を紹介されることはほとんどない。ましてや手術の前に「放射線と手術とどちらを選ぶかな」どと尋ねる医者はほとんどいない。それが実情である。
自分の命を守るために、可能性のある治療方法調べて、納得して治療を始めるのが理想的である。しかし金田信一郎さんのように、内外の論文を精査して、専門家の意見を聞いて納得できる道を選べる患者はそうそういない。
まずそうした医学に対する知識や、情報を集めて精査し選り分けるスキルがない。
ですから著者も、全ての人にこうした方法を勧めているわけではない。多くの患者にとっては「先生にお任せします」でいいのかもしれないし、ただ標準治療に従うことでも納得できるのならそれも良いでしょう。
ただ言えることは、金田さんのように徹底した調査ができなくても、主治医との信頼関係のもとで自分の納得いくまで質問をして、セカンドオピニオンも考えてみる。そうした主体性を持った患者が長く生き残っているのではないでしょうか。



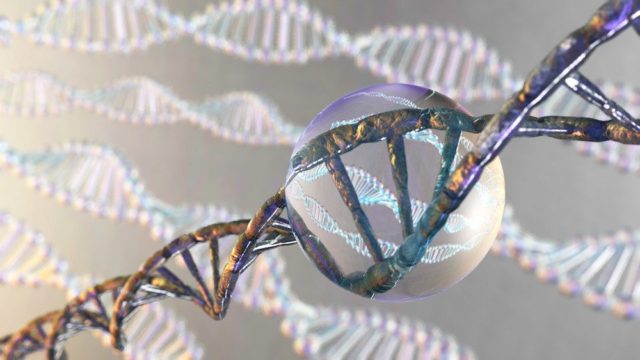


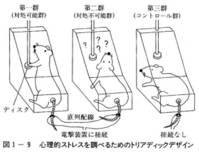





いつも更新ご苦労さまです
基本的に医師および病院は、自分のところでやってない治療法を
紹介することはありませんよね
例えば、もし腹膜播種になっていたとして、パクリタキセル腹腔内投与や
HIPECなどを行いたければ、患者が探して転院することになります
さらに、高齢化により自分で調べて行動できる患者も限られています
こういう状況にあって、「がん治療コーディネーター」のような存在が
必要ではないかと思うのです
コーディネーターは十分な医学知識と、どこの病院でどんな治療を
しているかの情報を持ち、しかしどこの医療機関にも所属しません
患者と面談し、十分時間をとって治療の目的や
どんな治療をしたいかの要望を聞き、
それに合った治療法や医療機関を紹介する
もちろん費用やリスクについてもしっかり説明します
さらに、主治医との面談やセカンドオピニオンの際にも
患者とともに面談にのぞみ、医師に質問したり患者にアドバイスを行う
そんな形ですね
万国旗さん。「がん治療コーディネーター」の必要性はわかります。しかし、中にはどこかの代替医療クリニックや企業と繋がっているのもあるので、その判断が難しいですね。無料でできるはずもないですし。
本来のEBMは、その考えを通じて患者個別の医療に向かうべきなのでしょうが、医療費の削減と結びついたのが不幸ではないかと考える次第です。
患者の要望にすべて応えるだけの医療資源はない、ってことでしょう。