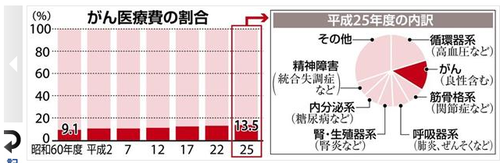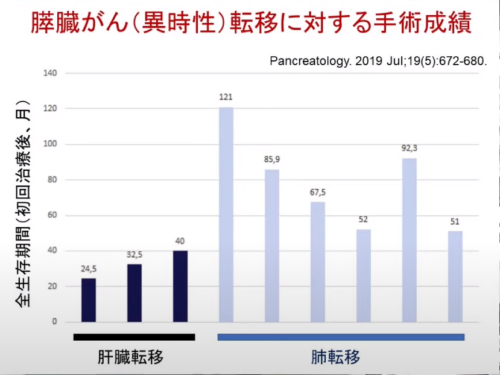今日の一冊(163)『もしもあなたの大切な人が末期がんになったら』

もう紫陽花の季節なのですね。蕎麦屋の暖簾の前にこの一輪だけが色づいていました。
雨です・・・

大学病院においてターミナルケアに従事していた臨床心理士である福山嘉綱さんが、ステージ4の胆管がんを宣告され闘病されていました。
夫を小腸がんで亡くした臨床心理士である堀弘子さんは、「聴き書き」というスタイルで、末期がん患者が自分の命の終わりをどのように考えているのか、カウンセラーとしてがん患者と接していた時と、実際に自分がステージ4の癌患者になった時、その違いはどういうところにあるのか、などを書き綴っています。
たくさんの闘病記がありますが、いずれやってくる「死」を真正面から捉えて本音を書いたものは少ないです。タイトルからは遺された家族のための本のようにも受け止められますが、末期のがん患者本人にこそ読んでほしい本です。
この本は、「命の終わりが見えてきたがん患者が、実際にはどのような思いでいるのかを知りたい」との堀さんの思いで実現しました。
死を前にしたがん患者が、最期の時間をどのように考え、どのように過ごそうとしたのか。がん患者によってはそれぞれ違うと思いますが、福山さんの、
副作用でよれよれの8ヶ月を過ごすくらいなら、最後の一か月を、痛み止めをして混濁状態で過ごすとしても、それまでの4~5ヶ月はピンピンしてるほうが、よほど自分が満足できるのではないかと思っています。
こうした思いは、周りからはなかなか受け止めてもらえず、「死に急ぐな」と言われてしまうのですが、呼吸をし、心臓は動いているけれど、自分のやりたいことはほとんど何もできない状態で過ごすよりも、あちこち行きたい所に行ったり、急に思い立ったことをやってみたりできる状態でいたいと願っています。
という言葉は、臨終のベッドでも抗がん剤の点滴が繋がれているような、「最後まで積極的な治療」を拒否する姿勢として共感が持てます。
先延ばしにしがちですが、「近いうちにやってくる死」に考えておくことも必要でしょう。
「人生会議」やアドバンス・ケア・プランニング(ACP)という言葉は出てきませんが、ACPのマニュアルにはない教科書としても推薦できます。
当事者とそれを支える家族の意識のずれ、葛藤も生まれがちです。それにどのように対応したのか。がん患者を支える家族にも読んでほしい本です。