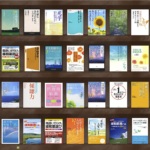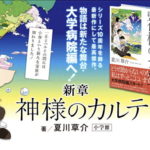お薦めの記事
参院選の争点にならない緩和ケア病棟入院料
問題の根っこには、安倍自公政権の社会福祉予算の削減にあるのです。
自民党と”福祉の”公明党政権は、「早期退院」の誘導を狙った診療報酬の改定、療養病床の削減、国公立病院の統廃合と病床機能の淘汰など、入院患者を強引に“追い出し”をする制度改変をずっと続けてきました。
これらの連続的な改悪によって、患者や家族の困難を増やし、「介護難民」「療養難民」「緩和ケア難民」を増大させることになっています。
さらに、安倍政権は2014年の法改定で導入した「地域医療構想」をてこに、都道府県に病床削減の計画をつくらせ、2025年の病床数を、本来必要とされる152万床から119万床に、33万床削減していく計画を推進しています。
「在宅療養」を進める政策をとり、社会保障予算を削減しようというのが、自公政権、厚生労働省の方針です。
しかし、これでは終末期のがん患者は、安心して最期を迎えることもできなくなります。
「ゆらぎ」を認めてこそ、個別化医療が成り立つ
医学は科学です。しかし、医学の対象とする人体は複雑系の代表であり、その行動は「非線形」に振る舞う。
したがって、医学を学問として捉えた場合、その方法論は「非線形」でなくてはならないはずです。
しかし、物理学でさえも「非線形」の扱いが始まったばかりなのに、その高次な応用科学である医学が、非線形の方法論を取り入れることは、ほどんど不可能でしょう。
その反面、医療は太古の昔から経験則に基づいた複雑系として扱われており、医療は元々非線形なのであり、医療の中に「ゆらぎ」を認めてこそ成り立ってきたのです。それが「さじ加減」と呼ばれ、そうした行為を太古から「医療」と呼び習わしてきただけのことなのです。
今日の一冊(117)「このがん治療でいいのか」
がんを克服するために一番重要なこと。それはがんについてエビデンス(科学的根拠)のある正確な情報を集め、よく吟味し、ベストの治療法を選択・実践することです。
がんは情報戦なのです。
ではがんについての正しい情報はどうやったら手に入るのでしょうか?
主治医(担当医)からの説明やガイドラインだけで十分でしょうか?
もちろん主治医は標準治療を勧めるでしょうし、ガイドラインを読めば、現時点での最良の治療法が分かるでしょう。しかし本当にがん患者さんが知りたい情報は、主治医も教えてくれませんし、ガイドラインにも載っていません。
本書では、がんと診断された患者さんが、実際の治療に対して疑問に思うことや、ぶつかりやすい問題点、そして意外と知られていないがん治療のトピックスについて、エビデンスに基づいて分かりやすく解説しました。
医者と患者のすれ違いはなぜ起きるのか?
「科学的な個別性」を患者は求めているわけですが、近年、個別化医療(プレシジョン・メディシン)に力を入れられています。患者の「自分に効く治療法」への要求にある程度は応えられる望みが出てきています。
しかし、まだまだ時間はかかりそうです。患者個人に対して、確実に効果のある治療法をする、そのために現場で使用可能な個別化ツールはまたアバウトです。
現状では、患者も医師も、未熟な部分にはある程度の妥協を許すという考え方が求められているのだろうと思います。
統計は、目前にいる生身の患者の代わりにはならない。統計は平均を表わすものであり、固体を表わさない。医薬品や治療に関する医師個人の経験に基づく知恵ー臨床試験の成績から得られた「ベスト」の治療法が、その患者のニーズや価値観に適合するかどうかを判断する医師個人の知識ーに対し、数字は補足的な役割でしかない。
ビタミンDでがんの術後5年生存率が改善
非小細胞肺がん患者155人を、手術後1年間、ビタミンDサプリメント(1,200 IU /日)を与えるグループとプラセボ群に分けて比較した無作為化二重盲検試験です。
再発および死亡はそれぞれ40人(28%)および24人(17%)の患者に発生した。全試験集団において、プラセボ群と比較してビタミンDに関して無再発生存期間(RFS)および全生存期間(OS)のいずれにおいても有意差は見られなかった。
しかしながら、分析を25(OH)Dが低い初期段階の腺癌を有するサブグループに限定することにより、ビタミンDグループはプラセボ群より、5年RFS(86%対50%、P= 0.04)およびOS(91%)が有意に優れていた対48%、P= 0.02)。
ビタミンDの血中濃度が低い患者に限れば、1日に1,200 IUのビタミンDサプリメントの摂取が5年生存率を改善するという内容です。
代替療法に関する私の考え方は、
1. ヒトに関してある程度の科学的根拠(エビデンス)がある
2. 重篤な副作用が無い
3. 長く続けるためには、小遣い程度で購入でき高価でない
です。その意味では、ビタミンDは無視するには勿体ないものです。