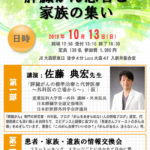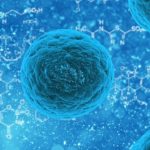お薦めの記事
ウイルス療法の第3相試験に中止勧告
腫瘍が縮小=延命効果がある、とはならないのががん治療の世界です。
(T-VEC)も、無増悪生存期間(PFS)については統計学的有意差はなく(従って、全生存期間(OS)の延長効果も期待できない)という結果になっています。
その一方で「経済毒性」は顕著です。
「T-VEC+ヤーボイ」の一回の治療費は5600万円あまり、ヤーボイだけの治療費は1500万円ですから、T-VECの治療費は4000万円ということになります。
第2相試験で顕著な効果が認められても、第3相試験でだめになる臨床試験は掃いて捨てるほどあります。
しっかりと第3相試験まで実施して、承認するかどうかの判断が必要でしょう。