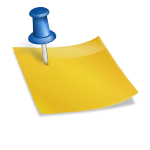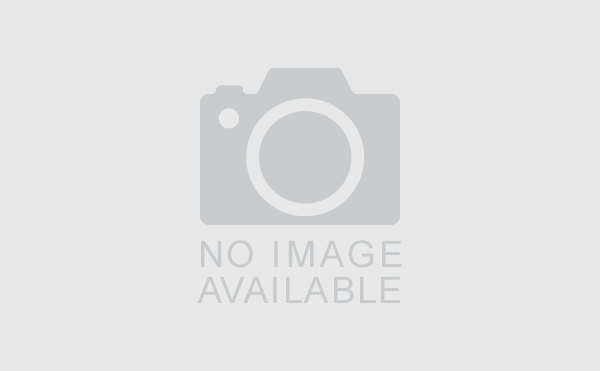ブリューゲルの絵
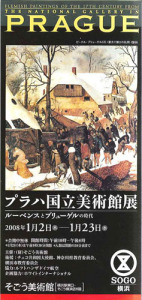
妻と娘の買物に付きあって車で送ったついでに、そごう美術館で開催中の「プラハ国立美術館展=ルーベンスとブリューゲルの時代」を見た。
ブリューゲルの細密画ともいえる作品に興味を持つようになったのは、中野孝次の「ブリューゲルへの旅」(文春文庫)を何年か前に読んでからだと思
う。「どの絵もいくら見ていてもあきなかった。ふしぎにしんとと静謐な世界に誘うものがそこにはあって、静かな声で、ここがお前の帰っていくべき場所だと
語りかけてくるようであった。・・・」と中野孝次が共鳴した「雪中の狩人」はなかったが、ブリューゲル一族の同じ題材での作品があった。
入場券にも印刷されていた「雪中の東方三賢王の礼拝」があった。東方三賢王とは、新訳聖書に出てくるベツレヘムで、イエスの生誕を祝い3人の賢王が
お祈りをする話である。この主題の宗教画は腐るほどあるが、ブリューゲルはこの三賢王の礼拝をなぜかベツレヘムでなく、彼の郷土フランドル地方に場面を設
定して描いている。彼の絵は素朴で単純で、ただ北国の粉雪の舞い落ちる冬の日の憂愁を帯びた日常を白い雪と茶褐色で描いているだけである。薪を束ねたり氷
を割ったり、雪道を前かがみで急ぎ足で雪道を急いでいる村人たちに日常生活が画面のほとんどを占めている。画面からはみ出してこぼれんばかりに一軒の藁屋
があり、そこに生まれたばかりのイエスを抱いたマリアがいる。そばに三賢王のうち二人が跪いている。あの人類史上の重大な出来事が、フランドル(英語なら
フランダース)の寒村で誰にも気づかずに起こっているのだ。金ぴか衣装も光輪も何一つなく、ただ無関心な村人の日常生活の中の出来事として描かれている。
ブリューゲルにとっては、人間の愚かしさ、貪欲、愚かさ、狡猾さもひっくるめた「日常」こそが描こうとした対象だったのだと思う。彼はそこにこそ人生の価値を見出していたのだろう。

「バベルの塔」は素晴らしいまでの中世都市の俯瞰図の真ん中にデンと異様な物体がある。画家が現場監督でもあったかのように、さまざまな建設道具ま
でが精密に描かれているが、建設途中のバベルの塔は、何故か崩壊の運命を予感させる。人間の技術や科学、そうした物に何の価値があるのか? この愚かしい
生を愚直に生きることが最大の生ではないのか。成長と発展を目的に築いてきた近代が、人類に本当の幸福をもたらすはずがないではないかと、ブリューゲルが
言っているように思えるが、どうだろうか。
マネーが徘徊する新自由主義経済も、実はバベルの塔なのかもしれない。