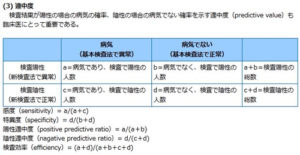「逆システム学」から癌を考えてみると・・・
児玉龍彦氏が、7月27日の衆議院厚生労働委員会において参考人として意見陳述した内容はすでに紹介したし、ネットでもマスコミでも話題になっている。国会で発言したチェルノブイリ膀胱炎や甲状腺がんのエビデンスに関する内容が、「逆システム学の窓」と題したエッセイで閲覧できる。
Vol.28「チェルノブイリ原発事故から甲状腺癌の発症を学ぶ」
Vol.41“チェルノブイリ膀胱炎”―長期のセシウム137低線量被曝の危険性
特集のタイトルとされた「逆システム学」は聞き慣れないが、岩波新書に『逆システム学―市場と生命のしくみを解き明かす (岩波新書)』との書名で、金子勝氏と児玉龍彦氏の共著がある。そこには、「近代科学における要素還元論と全体論という不幸な分裂を乗り越えてゆくために、逆システム学という方法を提唱することにたどりついた」とし、
まず筆者たちは、従来の要素還元論と全体論の分裂に対し、個と全体を結ぶ中間領域にある制度、調節制御のしくみに注目した。そしてそのしくみは<制度の束>と<多重フィードバック>によってできていると規定した。
実際、多重フィードバックが壊れてしまうと市場経済も生命体も維持することはできないからだ。
ところが、要素還元論は、この市場経済や生命体の本質である、制度の束と多重フィードバックを解析する方法を持っていない。
その点では、もう一方の全体論の系譜にある構造論や複雑系論も同じだ。筆者たちは、無前提的に本質を定義し、システムを構成する全体論も批判する。それでは要素還元論と同様に、市場経済や生命体の本質にせまることはできないからだ。
と、「逆システム学」を提唱した理由を挙げる。いわゆる三体問題、太陽・地球・月が相互作用する場合、ニュートンの運動方程式を厳密に解析的には解けないのであるが、それでも宇宙飛行士は月に着陸することができる。それは微細な誤差は無視してもかまわないと、経験的に知っているからであり、誤差が大きくなれば修正しながら飛べば良いからである。
シグナルとノイズの問題、すなわち、経験的に無視していい誤差なのか、重要なシステムの差異なのか、が重要な課題となる。この答えは、実験や治療、経済活動や経済政策における人間のシステムへの介入、働きかけへの結果が鍵となる。システム全体は不可知の領域を含みつつも、働きかけへの反応の予測ができれば、正しい政策、治療法の基礎となっていく。
システム全体をモデル化するような「複雑系」のような議論ではなく、システム全体はわからない段階でも、部分的に理解できている制度や制御のしくみをもとに、ある政策や治療の含みうる問題点を予測しようとする試みが逆システム学なのである。
児玉氏の国会での意見は、このような逆システム学の考えから行なわれたものだ。
チェルノブイリ膀胱炎といわれる、膀胱への低線量長期被曝により、前癌状態が観察されたという福島博士らの研究では、チェルノブイリ住民の尿中セシウム濃度は6Bq/リットルであった。いま福島の女性の母乳からは2~13Bq/kgというほぼ同じ濃度の放射性セシウムが検出されている。疫学的にはまだ証明されていなくても、この事実がシグナルであり、システム全体を予想して将来起こり得ることを推測できるのである。
9月14日の東京新聞「こちら特報部」には、その福島博士が登場して、今から対策を立てれば「福島膀胱炎が起きないようにすることは十分できるはずだ」と述べていた。山下俊一氏らのように「甲状腺がん以外の癌が増加したというデータはない」というエビデンス至上主義=要素還元論ではなく、典型的なデータからシステム全体を類推すること、言い換えれば、「早すぎる警告」をとらえて「予防原則」に立った対策が必要だということである。
『新興衰退国ニッポン』の「おわりに」には次のように書かれている。
リスク社会においては、近代実証科学はかえって有害な役割を果たす場合があることに注意を喚起した。そして、むしろ統計上の5%のはずれにこそ意味があると述べた。このはずれの5%に当たる「異常事態」が頻発する時こそが重要なのである。
自然現象であれ社会現象であれ、今や大きく非線形的に変化する、複雑な変化に直面している。一見すると、大きな変化は、複雑で多数の要因が重なり合っているように見える。だからといって、それが分析できないわけではない。異常な事態を病理の予兆と考えれば、異常な事態によって本質的なメカニズムが引き出されてくるのが垣間見えてくるからである。
癌の生存率曲線において、必ず右端に長く延びた曲線となる。いわゆる”恐竜の尾:ロングテール”である。この統計上のはずれである5%になることが、我々がん患者の願いである。5%の中には自然治癒などといわれる症例もあるはずだ。
逆システム学でいう典型的なシグナルは、自然治癒、驚異的回復、自然緩解であろう。このような症例は、体内のまだ不可知の”生体内システム”の結果として偶然現われたものではないか。あるいは、『がんに効く生活』に紹介されたデータにもそうしたシグナルがあるはずではないのかと考えられる。
分子標的薬であっても、癌細胞の関係するたくさんの情報経路、全システムのほんの一部に対しての薬である。人間の遺伝子の98%は調整系の遺伝子であり、そのごく一部に作用してみても、システムの全体がどのような反応をするかの予想が難しい。副作用の少ないはずの分子標的薬に思わぬ副作用が現われる道理である。
「がんは複雑系」だから、たくさんの要因が複雑に重なり合っている。その全システムを知るまで癌患者は待ってはいられない。臨床的に得られた、まだエビデンスとは言えないようなデータを使って、宇宙飛行士が月に着陸するように、癌患者も軌道修正しながら癌に対峙するしかないのだろう。
疫学的調査を待っていたら手遅れになるという児玉氏の指摘は重要であるが、しかし、水俣病などの過去の公害事件では、それ以上に政府の立場に立った医学者の役割が大きかったことを忘れてはならない。ある程度のエビデンスが揃った後でも「科学的に実証されていない。
メカニズムが明らかではない」として水俣病が有機水銀によるものだと認めるのに数十年かかった。この問題を津田敏秀氏が『医学者は公害事件で何をしてきたのか』で論じている。ここには、水俣病裁判において、情報バイアスを「マスコミによる情報操作」と勘違いしている国の代理人、医学者が疫学の専門家として出てくる。放射線について、にわか勉強した「放射線の専門家」が登場する現在の状況と酷似しているのに驚いてしまう。