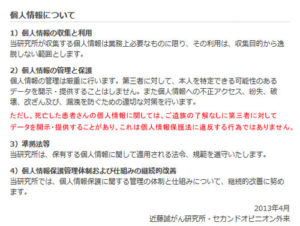ノーベル賞 戸塚洋二さんのこと
八千穂高原自然園の紅葉
二人の日本人にノーベル賞が授与されました。生理学・医学賞の大村智・北里大特別栄誉教授、物理学賞に東京大学宇宙線研究所の梶田隆章所長が受賞されました。
1997年からは東京大学宇宙線研究所長だった故戸塚洋二さんは「ノーベル賞に一番近い人」と言われていたのです。しかし戸塚さんは2008年に66歳で直腸がんのために亡くなります。その闘病の日々をブログに残していました。内容も多岐にわたり、科学、宗教、生と死、自然、宇宙にまで彼の考えを述べていました。
残念ながら現在は閉鎖されています。しかし、立花隆が『がんと闘った科学者の記録 (文春文庫)』として出版されています。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4167801353″ title=”がんと闘った科学者の記録 (文春文庫)”]
やはり科学者ですね。自分の癌のCT写真をデジタル化して、腫瘍の大きさを計測してグラフ化したり、抗がん剤の投与と腫瘍の大きさの関連性を論じてみたりと、科学者が故にデータを駆使して考察しようとする姿が書かれています。エックス線写真をビューアーの上に載せてデジカメをマクロモードにして腫瘍の写真を撮っています。Ca19-9やCEAの数値もExcelで時系列的に追っかけています。
冷静に自分のがんを見つめ、「私はがん克服を人生目標にしているのではありません。がんを単なる病気の一種と捉え、その治療を行っているに過ぎません」と言い切ります。勤務地の近くの草花や木々のこと、教育のことなどへの言及もあり、闘病記と言うよりはエッセイと言えると思います。壮絶な闘病記で、研究者としても立派な業績を残され、がんと正面から闘った姿には感動します。
残りの短い人生をいかに充実して生きるか考えよ、とアドバイスを受けることがあります。このような難しいことは考えても意味のないことだ、という諦めの境地に達しました。私のような凡人は、人生が終わるという恐ろしさを考えないように、気を紛らわして時間を送っていくことしかできません。
戸塚洋二さんでさえ「凡人は」というのですから、私のように正真正銘の「凡人」は有意義な生き方に迷ってしまいます。
佐々木閑氏の『日々是修行-現代人のための仏教100話』には、『ある物理学者との邂逅』と題して、戸塚洋二氏との仏教と物理との世界観の共通性について語らい合ったことなども紹介されています。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4480064850″ title=”日々是修行 現代人のための仏教100話 (ちくま新書)”]
そういう人が、「諦めの境地に達しました」と言うのですから、ずいぶんと考えた末の結論なのでしょう。是までと同じ人生を送ることもまた、「充実して生きる」ことに違いない。何も特別なことをすることもないし、急にそうした目的が見つかるはずもなかろう。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4044094470″ title=”科学するブッダ 犀の角たち (角川ソフィア文庫)”]
佐々木閑氏には『科学するブッダ 犀の角たち』という著作があって、これが抜群におもしろい。私は久しぶりに時間を忘れて読みふけりました。この本は仏教書です。著者もそのように書いているから仏教書なのでしょうが、直接に仏教のことに触れているのは、後ろの3分の1程度です。物理学、進化論、数学、更にベンローズの『皇帝の新しい心』に触れてから、やっと仏教論が始まるという、なんともおもしろい構成です。