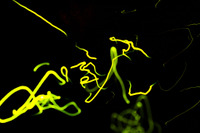良寛のこんな詩がいい
本ページはプロモーションが含まれています。

寝る前、まどろんでいると、
ふと、良寛のこんな詩が思い浮かんできた。
騰々(とうとう) 天真に任す
嚢中(のうちゅう) 三升の米
炉辺 一束の薪
誰か問わん 迷悟の跡
何ぞ知らん 名利の塵
夜雨 草庵の裡
雙脚(そうきゃく) 等閑(とうかん)に伸ばす
立身出世など考えもせずに、ただ万事なるがままにして生きてきたが、今こうしてひとり雨音を聞きながら炉辺で冷え切った足を伸ばして暖を取ることができることが至福の喜びだ。
頭陀袋(ずだぶくろ)には、乞食をしてもらってきた三升の米があり、暖を取る一束の薪がある。これ以上何が必要であろうか。
良寛のように飢餓の境で生きた真似はとてもできはしないが(しかし、大富豪のパトロンからもらった酒は飲んでいた)、名誉だの地位だの肩書きなど、競争や成果や他人の評価を気にして生きることが如何につまらないことかと思う。
今こうして痛みも悩みもなく、少し疲れた足を伸ばす気持ちよさをただ感じている。
二度もがんになると、人生で大切なものは何か、価値観もずいぶんと変わってくる。
良寛について多くの書籍を遺した中野孝次。彼の『風の良寛』にこの歌が紹介されている。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4167523124″ title=”風の良寛 (文春文庫)”]