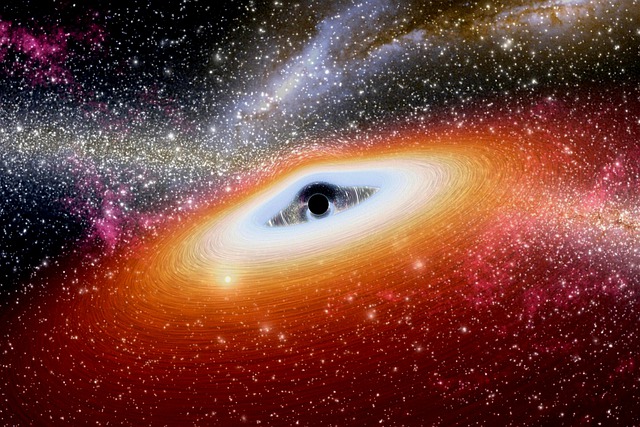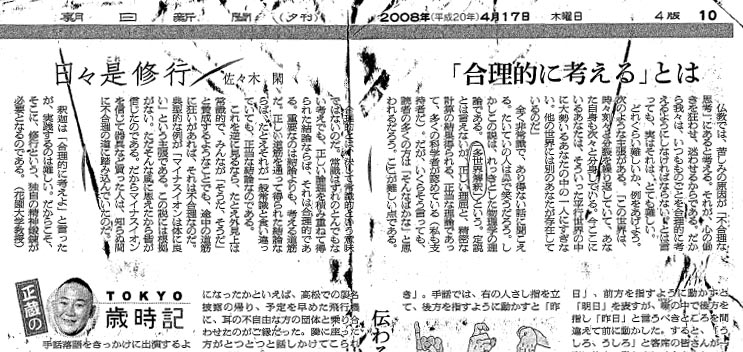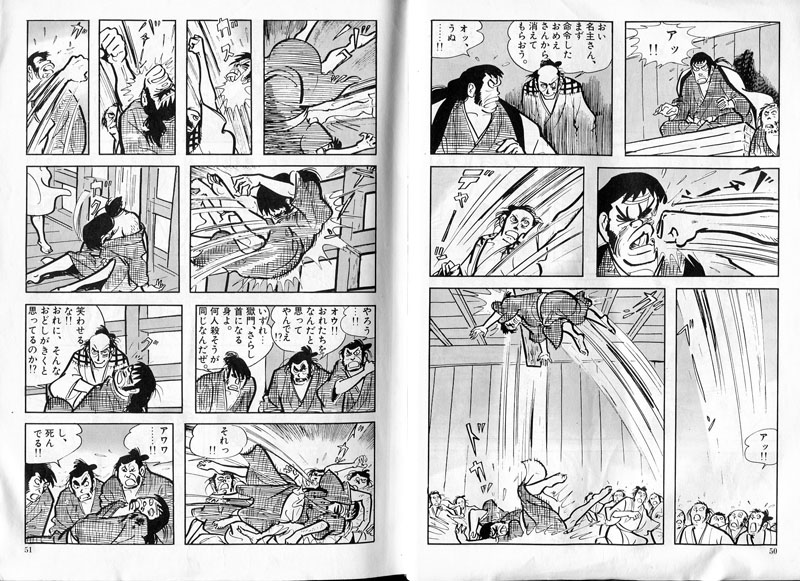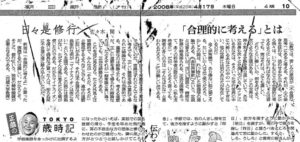心と癌と量子力学の関係(1)

『化学装置としての脳と心―リセプターと精神変容物質
』(リチャード・M・レスタック著 半田智久
訳 新曜社)は、精神変容物質が脳に作用する機構を解説したものであり、植物を使った精神変容の歴史から、精神疾患に対する薬剤の開発・発見の歴史を垣間見せてくれる。少量で精神世界を変容させてしまう薬物と、その受け手である脳内リセプターの話であるが、最終章では、量子力学を考慮したリセプターと情報伝達物質の結合が述べられている。
リセプターと情報伝達物質は、鍵と鍵穴に例えられて結合が説明されることが多い。ところが、化学構造が全く似ていない物質が結合してしまう時がある。問題は化学構造ではなく、鍵と鍵穴に相当する部分における電子配置なのだ。そして電子の相互関係は、量子力学的に考慮されなければならない。つまり、電子は太陽系惑星のように原子核を回る軌道上にある点として存在するのではなく、波動関数として表される雲のようにぼやーとした存在、電子が存在する確率(確率の雲)として考えられる。
今世紀はじめの30年間以降、量子力学は生物学のより深い部分にある不可思議を学ぶ手段としてたいへん有望視された。「最終的には生物学の概念と量子力学のメカニズムが結合することは当然の帰結である」と、すでに60年前にニールス・ボーアは書いている。そうした楽観論が今日ではあながち軽率なものとは言えなくなってきている。神経伝達物質とリセプターに関する研究は、脳内で起きていることが化学的な対話、化学物質の会話であることを明らかにしている。この分子の語り合いの場はリセプターにある。もっとも、スーパーコンピュータの出現までは、伝達物質とリセプターの相互作用に関わる膨大な計算量が理解の壁となっていた。それが今や高速コンピュータのおかげで、神経科学者たちは伝達物質とリセプターの問で生じている相互作用を予測する量子力学の理論や方法を使えるようになった。こうした研究からの洞察は伝達物質とリセプターの相互作用に関する今後の理解にとって刺激となるだろう。
既に製薬企業では、新薬の開発においてこうした量子力学的効果を考慮したコンピュータプログラムを使っている。
伝達物質とリセプター間の相互作用では、一方の分子内の電子がちょうど磁石のように力を及ぼし、他方の分子内の電子の空間配列に影響を及ぼす。つまり、相互作用はリセプターに影響する伝達物質を基にするのでも、その逆でもなく、相互に影響し合う力の場に由来するのである。分子の力の場はそれぞれの構成要素によって決まる。分子の特性やリセプターのような別の分子が存在するときの分子の挙動は、電子の波動関数(波動関数はある分子内のすべての電子の推定空間分布と配列を数学的に表現する)とそのエネルギーレベルを分析することによって推測することができる。そうした情報を携えて、神経科学者たちは薬の作用に関わる分子基盤を理解しつつある。
量子に関する原理によって、近い将来、分子配置によって薬物とりセプターの親和性を理解できる可能性が高まってきた。神経科学者たちは化学構造がまったく似ていないのに電子配列が非常に近似しているため、リセプターと作用し合うような化学物質をすでに見出している。すなわち、リセプターへの薬の適合性には単に構造的、形態的なものだけでなく、動態的な性質も関わっているのである。大部分の薬が非選択的に結合する事実、つまり特定のリセプターだけでなく、構造的に見ただけでは予期できない部位にまで結合する理由のひとつはここにある。
化学的結合を考慮するためには、双方の物質間の力の場による電子配置の変化を考慮にいれる必要がある。
情報伝達物質(サイトカイン)は脳内だけで働いているのではない。身体の至る所で働いている。白血球にも脳で作られるホルモンのリセプターがあることがわかっている。がん細胞と白血球との闘いにおいても、その働きの根本は化学反応であり、情報伝達物質とリセプターが主役である。
脳の働き、心の有り様が、がんに対する免疫力(白血球の働き)に影響していることが、量子力学的に説明できる日も近いはずである。『病は気から』という言葉には量子力学が関わっているのである。