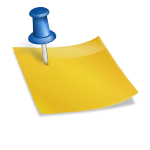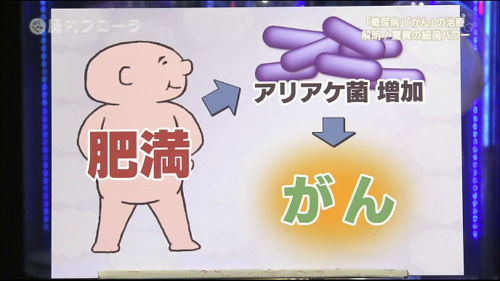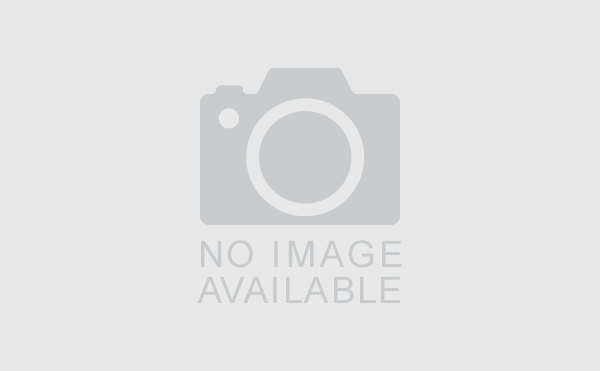エビデンスの信頼性に疑問符!

臨床試験において、最も信頼度の高いのがメタアナリシスとランダム化比較試験(RCT)であるが、一方でこうした指摘もある。
米Oregon Health and Science UniversityのRosa Ahn氏らは、臨床試験の主任研究者と治験薬製造会社との金銭関係は、ポジティブな結果を報告する独立した要因になるという仮説を立て、2013年に発表されたランダム化対照試験(RCT)の論文を検証し、金銭関係がある場合は実際にポジティブな試験結果が多かったと報告した。結果はBMJ誌電子版に2017年1月17日に掲載された。
製薬企業が金を出している臨床試験は、治療に効果があるという結果が出やすいということだ。
医師でありサイエンスライターでもあるベン・ゴールドエイカーが、イギリスにおける製薬企業の悪役ぶりを紹介している。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4791768647″ title=”悪の製薬: 製薬業界と新薬開発がわたしたちにしていること”]
臨床試験の多くが製薬業界の試験援助で行われるが、外部資金に頼らない臨床試験に比べて実際以上に見える肯定的な結果を生みやすい。コレステロール低下薬スタチンの例では、192件の臨床試験のうち、業界の資金援助を受けた臨床試験は、そうでない試験に比べて好意的な結果を出す割合が20倍も高かった。
スタチンが特別なのではない。精神治療薬でも抗がん剤でも糖尿病治療薬でもほとんど同じ傾向である。 そうした試験では、肯定的な結果を出すためにあらゆる手法を使う。臨床試験の対象患者は、既往症のない、若い、大量の薬を服用していない、アル中ではない、身体状況(PS)のよい「理想的」な患者ばかりであり、現実の治療現場の患者とはかけ離れている。既に効果が認められている治療薬があるにもかかわらず、試験対象の薬とプラセボとを比較する。つまり、「無いよりはまし」な薬でも統計的有意差が証明できる。
さらには、否定的な臨床試験の結果は公表されない可能性が高い。これは「公表バイアス」と言われるものだ。抗うつ薬レボキセチンとプラセボとの比較臨床試験は7件あったが、1件だけ肯定的な結果が出て学術雑誌に発表された。しかし、その10倍の患者を対象とした試験では否定的な結果となり、これはどこにも発表されなかった。抗がん剤、タフミル、コレステロール低下薬、肥満治療薬など、どの薬でも同様であって、否定的な論文を公表しないことで、本来なら死ななくても良いはずの何十万人もの患者の命が奪われている。
医学会のオピニオンリーダーとされる医者には、講演料などの名目で多額の金が製薬企業から渡っている。彼らは資金提供元の企業の薬を「より多く勧め、肯定的に論評」する傾向がある。世界的に権威があるとされる学術誌「ランセット」や「JAMA」「NEJM」誌に対して、製薬業界は広告として一社当たり年間1000~2000万ドル支出している。業界全体としては年間5億ドルを学術誌に広告費として支出しているのであり、「権威のある」これら雑誌の収入の多くが広告費に依存しているのである。
規制機関と業界の癒着の深刻さ、治験結果の改ざんと隠ぺい、研究論文の多くが製薬会社が雇ったゴーストライターによって代筆され、内容がねつ造されている。 高血圧薬のディオバン事件で明らかになったように、日本でも例外ではない。臨床試験のプロトコルを計画し、患者を集め、結果の統計解析をする(場合によっては論文を書く)のは多くは製薬会社の人間である。 臨床試験のアウトソーシング化、巧妙なマーケティング戦略などなど、目を覆いたくなるような実態が次々と披露されている。
『ビッグ・ファーマ―製薬会社の真実』 という本にはもっと赤裸々に書かれている。
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4884122623″ title=”ビッグ・ファーマ 製薬会社の真実”]
著者のマーシャ・エンジェル氏は、ランセットと並び世界的権威を持つといわれるニューイングランド医学雑誌(NEJM)の元編集長。彼女が製薬会社のあくどさにやむにやまれず書いたというこの本は、当時大きな衝撃を与えたと言います。「有名医学雑誌の編集長という仕事 は、・・・医学界をリードする医学の守護神のはずだ。その医学の守護神が、こんな奴らは信用なりませんよと、医学界、製薬業界、臨床医たちを激しく追求する。」とあとがきにある。
今ではエビデンスそのものが商売道具になっている。