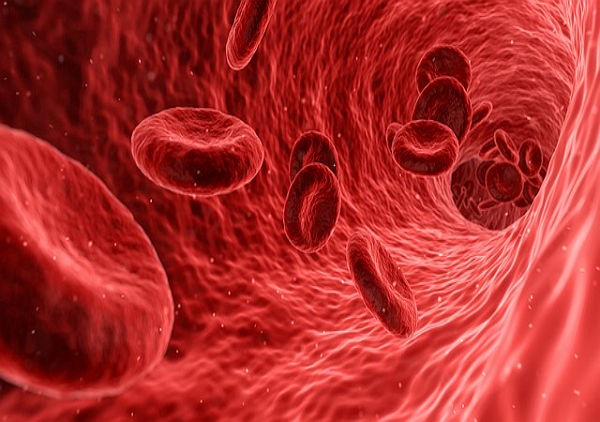今日の一冊(181)『ビタミンDでがんの死亡・再発を予防する!』浦島充佳
本ページはプロモーションが含まれています。
ーー 目次 --

今年、絶対にお勧めしたい最強の一冊です。
このブログでは、ビタミンD はがん患者にとって必須のサプリメントであるとして、度々紹介をしてきました。
この度、東京慈恵会医科大学教授の浦島充佳先生が、たくさんのエビデンスをもとに、ビタミンDががん患者にとってどのように役立つのか、どのような服用の仕方が有効なのかなど、具体的に明らかにしてます。
こちらの過去記事では、東京慈恵会医科大学の浦島先生たちの研究を紹介しています。
最初に重要な結論を先に書いておきます。
大切な要点
- ビタミンDサプリメント(1日2000IU)を接種した消化器がん患者の再発・死亡リスクが73%低下した。
- がん患者は1日2000IUの摂取が推奨される(下の商品で2粒/日)
- アメリカの内分泌学会は、健康維持のためには血中25ビタミンDが充足している場合でも、1日2000IUの摂取を推奨している。(日光浴だけでは不足!)
- ビタミンDのがん予防効果は、すぐに現れるわけではなく、服用を開始してから1年から2年近く経ってから見られます。効果を実感するまでに時間がかかるため、根気強く飲み続けることが大切です。
著作の内容を、私なりの考えから要点をまとめて紹介します。
ビタミンDとがん予防・治療の可能性
概要: 本資料は、ビタミンDががんの予防および治療(特に「死ぬがん」に対する効果)の可能性、その作用機序、および関連する臨床試験(アマテラス試験、VITAL試験、サンシャイン試験など)の結果について詳細にレビューする。また、ビタミンDの補給方法や推奨摂取量についても触れる。
主要なテーマと重要なポイント
ビタミンDの性質と役割の認識の変化
- かつては骨の健康に不可欠な栄養素として主に認識されていたビタミンDだが、2000年頃を境にその認識が変化した。
- 体内で活性化される前の前駆体である25ビタミンDが、全身の細胞の遺伝子発現を調整し、細胞の機能、分化、成長などを制御する機能的に重要な代謝物として認識されるようになった。これは、25ビタミンDレベルが人間のゲノムの数%から10%の発現をコントロールしていることを意味する。
- ビタミンDは食品からの摂取よりも日光(紫外線)によって皮膚で合成されることの方が多い。この点から厳密にはビタミンではなく、ステロイドホルモンの一種である「Dホルモン」とも呼ばれる。
- 25ビタミンDの高用量のビタミンDサプリメント(例えば1日2000IU)を摂取しても、血中活性型ビタミンDのレベルは厳密にコントロールされているため、高カルシウム血症や尿路結石になることはほとんどない。(活性型ビタミンDは医薬品であり、これらの副作用があるが)
- ビタミンDサプリメントは食品に含まれるものと同じなので、血中25ビタミンDレベルは上がりますが、 活性型ビタミンDが増えるわけではないので、 高カルシウム血症には理論上なりません。
- 医師であっても25ビタミンDと活性型ビタミンDの区別がついていないことが多い。
ビタミンDの抗がん作用のメカニズム(仮説)
- ビタミンDは、細胞内のビタミンD核内受容体(VDR)と結合し、細胞の核に移行してDNAのプロモーター領域に結合することで、数百から数千種類の遺伝子の発現を調整すると考えられている。
- 特に、細胞のがん化を防ぐブレーキとして機能するがん抑制遺伝子の一つであるp53遺伝子の働きに関連すると考えられている。紫外線などで遺伝子に傷がつくと、p53が誘導されて遺伝子を修復するか、修復できない場合は細胞を自滅させる。しかし、p53遺伝子自体に傷がつくとこの機能が失われ、がん化が進む。
- がん細胞の核内にはビタミンD受容体が過剰発現していることが多く、特にp53陽性がんでその傾向が著しい。
- ビタミンDは、がん細胞内のMDM2というタンパク質の量を増やすことで、p53タンパク質の分解を促進し、がんタンパク質としての機能を失わせるというメカニズムが仮説として提唱されている。
- また、ビタミンDは免疫チェックポイント阻害薬のターゲットとなるPD-L1の発現を抑制する可能性が示唆されている。がん細胞が免疫の監視から逃れる「免疫逃避機構」においてPD-L1が重要な役割を果たしているため、ビタミンDがこれを抑制することで抗腫瘍免疫応答を促進する可能性がある。
臨床試験によるビタミンDのがんに対する効果の検証
- アマテラス試験(消化管がん患者対象): 手術後の消化管がん患者417人を対象に、ビタミンDサプリメント(1日2000IU)またはプラセボを摂取する群にランダムに割り付けた二重盲検ランダム化プラセボ比較臨床試験。
- 当初の解析では統計学的に有意な再発・死亡リスクの抑制は見られなかった(ハザード比0.76, P=0.18)。
- しかし、事後解析により、p53陽性のがん、特に免疫染色で「真ッ茶色に染まる」ような高p53陽性がんで、かつ血清抗p53抗体陽性の患者に絞って解析したところ、ビタミンD群では再発・死亡リスクがプラセボ群と比較して73%も低下していた(ハザード比0.27, P=0.002)。これは過去の論文データでこれほど高い効果が示された例がなく、「目覚めるようなきれいな結果」と評されている。
- ビタミンDの抗がん作用は、内服を開始してから1年~2年目以降に現れる傾向がある。これは、ビタミンDが遺伝子発現を介して細胞の性質を変化させるのに時間が必要だからと考えられている。術後1年未満で再発するような進行の速いがんには、ビタミンDサプリメントは有効ではない可能性がある。
- VITAL試験(健常人対象): がんを発症していない健康な約2万5000人を対象に、ビタミンDサプリメント(1日2000IU)を摂取する群とプラセボ群にランダムに割り付けた一次予防試験。
- がん全体の発生リスクを抑制する効果については、ビタミンD群とプラセボ群で大きな差はなかった。
- しかし、サプリメント開始から2年目以降にがんで亡くなった人数を比較すると、ビタミンD群はプラセボ群よりも25%少なかった(ハザード比0.75, 統計学的有意差あり)。これは、ビタミンDサプリメントが「死ぬがん」の死亡を予防する効果があることを示唆する。
- 「死ぬがん」(転移したり死亡したりする進行の速いがん)の発生リスクに絞って解析すると、ビタミンDサプリ開始後1年半は差がほとんどないが、それ以降はビタミンD群の方がプラセボ群よりも「死ぬがん」の発症が遅く、最終的に発症リスクを17%減らすことができた(ハザード比0.83, 95%信頼区間0.69-0.99)。
- メタ解析: 世界中で実施されたビタミンDサプリメントを用いた二重盲検ランダム化プラセボ比較臨床試験のデータを約10万人分集めたメタ解析の結果、「毎日ビタミンDのサプリメントを摂取していると、がんの種類に関係なくすべてのがんの死亡率を12%減じ得る」ことが証明された。さらに、がんを発症してから毎日ビタミンDを摂取した場合でも、がんの死亡率が9%下がっていた。
「死ぬがん」と「死なないがん」の概念
- がんはその進行スピードや性質によって「死ぬがん」と「死なないがん」に分けられる。「死なないがん」は進行が遅く性質も穏やかで、検診で見つかるがんはこれが多い。一方で「死ぬがん」は進行が速く、治療が難しいことが多い。
- がんのスクリーニング検査は「死なないがん」を中心に発見しており、「死ぬがん」による死亡者数を減らす効果は限定的である可能性がある。
- ビタミンDは、「死なないがん」よりも「死ぬがん」に対してより有効である可能性がアマテラス試験の事後解析によって示唆された。
- ビタミンDの摂取方法と推奨量:
- ビタミンD不足・欠乏は血中25ビタミンDレベルで判定される。日本では20ng/ml未満が欠乏、20-30ng/mlが不足、30ng/ml以上が充足とされる。
- 厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)では、18歳以上の1日の摂取目安量は8.5µg(340IU)に引き上げられているが、これは骨の健康維持に必要な最低ラインであり、がんなど他の疾患予防のためにはより多く摂取する必要があるという説が主流である。
- アメリカの内分泌学会は、健康維持のためには25ビタミンDが充足している場合でも1日2000IUの摂取を推奨している。
- 慢性疾患(がん、心血管疾患、自己免疫疾患など)の予防のためには、毎日2000IUのサプリメント摂取が推奨される。効果が現れるまでに1~2年かかるため、継続が重要である。
- 季節性の急性感染症(インフルエンザなど)の予防には、そのシーズンだけ集中的に摂取する方法が効果的である。摂取開始から約10日~20日程度で効果が現れる。普段ビタミンDを摂取していない人は、1日数百万単位でも効果が得られる可能性がある。
- 日光浴によるビタミンD合成も重要であり、晴れの日なら15~30分程度、曇りの日や冬場は30~60分程度の週3回以上の推奨が一般的。手のひらだけの日光浴も有効。
- 高用量摂取に関する注意点として、1年分の高用量ビタミンDを一括で投与した試験では、転倒や骨折のリスクが増加するという逆効果が見られた。これは、ビタミンDの血中濃度を急激に上げることで免疫反応が鈍化する可能性が考えられている。毎日1000~2000IU程度の摂取が推奨される。
その他のビタミンDの可能性
- ビタミンDは、インフルエンザA+B、心筋梗塞、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、認知症、関節リウマチなどの自己免疫疾患の予防にも効果が期待できることが、臨床試験やメタ解析で示唆されている。
- 特に、心筋梗塞のリスクを約2割、妊娠高血圧症候群を35%予防できるという結果が出ている。
- 認知症予防については、ビタミンB12の同時摂取が効果に寄与している可能性も示唆されている。
結論
- ビタミンDは、特に進行の速い悪性度の高いがん(「死ぬがん」)の再発や死亡リスクを抑制する可能性が高いことが、信頼性の高い臨床試験やメタ解析によって示唆されている。その効果は摂取開始から1~2年以降に現れる傾向がある。
- ビタミンDサプリメントは、推奨量を守れば安全性も高く、医師の処方箋なしで安価に入手できるため、がん患者にとって「第6のがん治療」となる可能性を秘めている。
- 慢性疾患予防のためには毎日2000IU程度の摂取が推奨され、季節性感染症予防のためにはシーズン中の集中摂取が効果的である。
- ビタミンDはがんだけでなく、心血管疾患、自己免疫疾患、感染症など様々な疾患の予防にも効果が期待されており、「スーパービタミン」と呼ぶにふさわしい存在である。
今後の展望
- アマテラス試験の結果を踏まえ、p53陽性のがん患者に絞った「アマテラス2試験」が開始されており、更なる詳細な検証が期待される。
- ビタミンDが持つ多様な生理機能、特に免疫系への作用機序について、更なる研究が進むことで、その効果がより明確になることが期待される。
懸念点
- 現時点では、ビタミンDががんに対する標準治療(手術、抗がん剤、放射線療法など)に取って代わるものではない。あくまで補助的な役割として期待される。
- ビタミンDの効果を過信せず、医師の指示に従った適切な治療を受けることが重要である。
- 高用量の一括摂取は逆効果となる可能性が示されており、推奨される摂取方法を守る必要がある。