がん患者が考える「生」と「死」
ーー 目次 --
生きて死ぬ智慧
元気なうちに死について真剣に考えることができるのは、がん患者の特権です。誰しも死について考えることはあるに違いないが、がん患者は、数ヶ月先、運が良ければ数年先に手の届くところにある死を、我が身に確実に起こる事象として認識せざるを得ない。
私の弟は交通事故で即死だったから、死について考えることも、準備もする余裕もなく逝ってしまった。がんならじっくりと考える時間がある。せっかく与えられたチャンスだ。存分に使わなければもったいない。
 柳澤桂子さんが『生きて死ぬ智慧
柳澤桂子さんが『生きて死ぬ智慧』をいう本を出している。2004年の初版を持っているから、その当時買ったのだろうが、深く読みもせずに埃をかぶって放ってあったものを引っ張り出してきた。
般若心経を彼女なりに「心訳」した本である。生命科学者である彼女は、マウスの遺伝子研究で世界的な成果を出そうとしていた矢先に原因不明の難病に冒される。
どこの病院でも原因が分からず、「心身症だ。症状が多彩で医学的にあり得ない。気のせい、気持ちの持ち用だ」と言われ続けて、絶望的になり、最後は寝たきりになる。尊厳死まで考えるようになったとき、友人の紹介で精神科医である大塚明彦医師の往診を受ける。大塚医師は彼女の話を聞いただけで、「慢性疼痛、脳の代謝異常です」と診 断。抗うつ剤を投与して劇的に回復した。病名が付くまでに30年も経過していた。
断。抗うつ剤を投与して劇的に回復した。病名が付くまでに30年も経過していた。
こうした経緯は『いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる』に詳しく書かれている。
神秘体験
その彼女があるとき、神秘体験をする。一冊の本『人間の生きがいとは何か』(橋本凝胤)を夜が白々と明けるころまで読んでいたときのこと、
白く浮かび上がった障子を眺めていた私は、突然明るい炎に包まれた。
熱くはなかった。ぐるぐると渦巻いて、一瞬意識がなくなった。
気がついてみると、それまでの惨めな気持ちは打ち払われ、目の前に光り輝く一本の道が見える。
私は何か大きなものにふわりと柔らかく抱きかかえられるのを感じた。その道はどこへ行くのかわからなかったが、それを進めばよいことだけははっきりわかった。
「そうだ。生きるのだ。仕事をしなくたってきっと生きられる」
生命科学者である彼女は、しかし、「一般に、動物が強いストレスにさらされたときに、脳内快感物質が出るということは十分に考えられることである。たくさんの快感物質が出たときに、・・・・感覚が生じても不思議ではない。神経の過度の緊張は、火となって感じられる可能性がある。したがって、神秘体験は、神秘ではなく、科学で十分に説明のつく現象であろうと私は考える。」と冷静である。
しかし、そうした彼女も「癒しようもないほどに病んだ肉体とは裏腹に、今を必死に生きようとしている私のいのちの感触を、こころの奥に探り当てる。もはや滅び去る身とされた者が、救いを希求するこころの形見のような信仰への激しい渇望を、そこに実感する。」と書いて、信仰を求めていく。
般若心経に行き着く
ただ、「手近にある教団や教祖にすがりつくような宗教のかたちには満足できなかった」彼女が行き着いたのが「般若心経」の「空」の考え方でした。
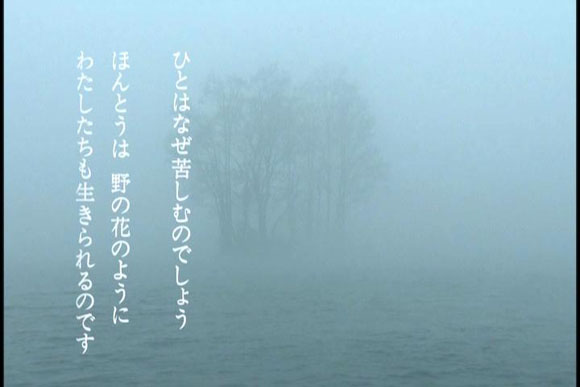
ひとはなぜ苦しむのでしょう・・・・
ほんとうは
野の花のように
わたしたちも生きられるのです
**************お聞きなさい
私たちは 広大な宇宙のなかに
存在します
宇宙では
形という固定したものはありません
実体がないのです
宇宙は粒子に満ちています
粒子は自由に動き回って 形を変えて
おたがいの関係の
安定したところで静止します
**************お聞きなさい
あなたも 宇宙のなかで
粒子でできています
宇宙のなかの
ほかの粒子と一つづきです
ですから宇宙も「空」です
あなたという実体はないのです
あなたと宇宙は一つです

「空」と「粒子」と彼女が言うとき、「空」は量子場のエネルギーであり、「粒子」は物質の粒子であるが、物質が粒子と波動の二重性を持っているということを暗示しているように思える。
真空場(波動)からあらゆる粒子が生まれ、そして真空場に帰って行く。光も電子もその他の粒子も波であり粒子でもある。これについては後で触れることにして、彼女の生命科学者の面を見てみる。
生命科学者から見た死
 『われわれはなぜ死ぬのか ――死の生命科学 (ちくま文庫)
『われわれはなぜ死ぬのか ――死の生命科学 (ちくま文庫)』では「死」を生物学的に考察している。
多細胞生物が雌雄の別を持ち、つまり性を得ることによって、雌雄の間で遺伝子のシャッフルができる。こうして多彩な遺伝子を持った固体が生まれることにより、変化する環境に適応していく可能性が大きくなる。
現在において性を持った多細胞生物が繁栄しているのは、進化の過程において性を得て、他の生物よりもより順応してきた結果である。そして遺伝子がシャッフルされた新しい個体が生まれると同時に、元の個体は死ななければならない。そうでなければ古い遺伝子と新しい遺伝子の合体が生じることになり、種の繁栄という性の目的に反するのである。
つまり、「性=生」が生じたことにより「死」は必然的に現われるようになった。
われわれの感覚では、生きているものが死ぬのであるが、生物学的に見れば、死ぬことによって、そうした戦略をとることによって種の繁栄が確実になるのであるから、「死ぬから生きることができる」のである。ひとつの個体が永遠の命を持たないことによって、種としての生が保証されるのである。
三六億年の生命の歴史のなかに時をおなじくして自己意識と無を認識する能力をあたえられ、死の刻印を押されたものとして、また、死をおそれることを知ってしまったものとして、おたがいに心を通わせ合い、深く相手を思いやることが、生の証のように思えるのである。
死ばかりでなく、老いもまた避けることのできない私たちの運命である。個体の寿命がのびたことによって、老いの苦しみを感じる期間も長くなっている。老いていく人々の苦しみを思いやるとともに、そこから多くのものを学びたいと思う。
私たちは、死を運命づけられてこの世に生まれてきた。しかし、その死を刑罰として受けとめるのではなく、永遠の解放として、安らぎの訪れとして受け入れることができるはずである。
また、死の運命を背負わされた囚人として生きるのではなく、誇りと希望をもって自分にあたえられた時間を燃焼し尽くすこともできるはずである。
今日も私たちは死にむかって百を歩んだ。夕日に向かってその百を思うとき、死への一日としての重みにたえる時を刻んだということができるであろうか。
同じ主張は、田沼靖一氏がより多くの著作で展開している。

「死」はなぜあるのか
20世紀の生命科学が明らかにした事実のなかに、「ヒトは進化の過程で可老可死を選択した生物から生まれてきた」ということがある。私たちは生命サイクルのなかに「死」を組み込んだ生物の末裔なのです。
細胞の「死」には3つの形態がある。
- ネクローシス-「事故死」。遺伝子に支配されない突発死
- アポトーシス-遺伝子による「自死」
- アポビオーシス-非再生系細胞の死:「寿死」=個体の死
火傷などにより細胞が壊死するのがネクローシスで、遺伝子が関与しない突発的な死であり、ウイルスや放射線等の影響を受けて再生不良となった細胞が、自ら遺伝子に組み込まれたプログラムを発動して自発的に死んでいくのがアポトーシスである。
神経細胞、心臓の心筋細胞のように、生涯置き換わることのない細胞の死をアポビオーシスという。遺伝子にプログラム化された2種類の細胞死を備えることによって生物の個体は有限の命をセットされているのです。
再生系細胞には分裂寿命がある。だいたい50~60回分裂すると、それ以上分裂増殖できなくなります。その仕組みは、染色体の末端にあるテロメアという特殊な構造がカウンターの役割をしているようなのです。
命の回数券
核のなかの染色体はDNAとタンパク質の複合体で、ヒトの場合23対46本があり、母親と父親から受け継いだ二重らせん状のDNAのひもが入っています。この二重らせんの末端に「TTAGGG」という六文字の塩基配列の繰り返しが百回ほども続いています。細胞が分裂するたびにこの「TTAGGG」の単位が約20個ずつ短くなることがわかっています。そしてこの長さが半分ほどになると、染色体の構造が維持できなくなり、やがて細胞は死ぬことになります。つまりテロメアは「命の回数券」のようなものです。
一方で非再生系の細胞は、徐々に機能が衰えて老化し、ある時間を経過するとこれも遺伝子に組み込まれたプログラムによって死んでいく。これは「命の定期券」といってもよいでしょう。
アポトーシスとアポビオーシスにおける細胞死においては、DNAがきちんと切断されている。つまり、細胞の持っている情報がすべてリセットされ消去されている。アポトーシスによる細胞の死によって、生体の中で余剰に作り出された細胞、機能を果たし終え老化した細胞、がん細胞などの有害となる異常な細胞を除去するという生体防御の役割を果たすことができ、固体の生が保証されます。
また、アポビオーシスによる細胞死とその延長線上にある固体の死によって新しい遺伝子の存続が保証されるのです。遺伝子が新たな遺伝子として存続していくためには、細胞及び個体レベルで確実に古い遺伝子を無にすることが必要なのです。
死はどのように生じたか
細胞が遺伝子に死を宿すようになったのは、進化における有性生殖の獲得過程で死が必要になったからだと思われます。減数分裂によって精子と卵子ができるが、そのときランダムな遺伝子の組み換えが起きる。精子と卵子が合体して新しい受精卵が生まれ、その中から環境に適さない遺伝子を持った固体が自然淘汰されます。「死」を遺伝子に組み込むことで新しい環境に適用した固体を残すということが可能になり、この戦略を持った生物が現在生き残っている、言い換えれば種の生存という目的に最もかなった戦略として「死」を選択した遺伝子が勝ち残っているのです。
無性生殖の方が遙かにエネルギーが少なくて済み、安全である。にもかかわらず有性生殖を持つ生物が進化的に発展してきたのは、遺伝子のシャッフルによって多彩な遺伝子を持った固体が生まれ、その中には環境の激変にも適応できるものが生じてきたからです。
5億4000万年前に第1回の種の大量絶滅期があり、4億4000万年前に2回目、3億6700万年前に3回目(これは隕石の衝突によるとされている)、2億5000万年前には火山噴火による大量絶滅期、6500万年前には小惑星の衝突によると思われる6回目の大量絶滅期を、地球の生物は経験している。しかし、それでも生き残る種があったから今日の地球上の生物がある。
有性生殖と新しい遺伝子を生成する「死」があったからこそ、今日我々は生存しているのです。環境の激変にあっても子孫を残すという生物の目的のためには「性」と「死」を獲得することが最も合理的な戦略だったということです。
無性生殖をする生物に限れば、ドーキンスが言うように遺伝子は「利己的」なのかもしれないが、有性生殖をする生物ではむしろ、自己が死ぬことで種を生存させるのであるから、遺伝子は「利他的」な存在ということができよう。
「死」を避けて生き続けようとすることは、「生」そのものに反する行為であり、遺伝子の存続と生物の多様性を否定することでもあるのです。細胞死による利他的な自己消去能こそが生命の摂理の根底にあり、「死」なしでは新たなアイデンティティを持った固体の創生は望めないし、存続もできないことになります。
私たちは他のために生きる存在
死の遺伝子が本来的に利他的であるとするならば、私たちの固体も、究極的には他のために生きるべくして生まれてきたと言えるのではないでしょうか。人間は自分の子孫の繁栄ばかりではなく、他者もそしてすべての生命を救うことを目的として生きる「命」を与えられた存在であることを、「死」の遺伝子は語っているのかもしれません。
有性生殖と「死」による遺伝子のシャッフルがなければ、「個」のアイデンティティも生まれようがなく、「個」のアイデンティティの時間的蓄積が「死」によって完結することを考えれば、「死」は「生」の別名だということになります。
心を再生し、今、ここに生きよ
可老可死のなかで自分の夢を追求し、与えられた時間のなかを自由に生きることで、人間の本来の姿が見えてくるのではないでしょうか。だとするならば、不老不死を願い身体を再生することを願うのではなく、こころを再生することが、がん患者に限らず全ての人間にとって「命」を生きることになるはずです。「今、ここに生きよ」と多くの賢人が言ってきたことが、最近の生命科学の観点から「死」をとおして眺めてみると、より一層理解できるような気がしてきます。
ヒトは、進化の過程で可老可死を選択することで生き残ることができた生物の末裔なのです。
私という存在は何か?
柳澤桂子が「私たちは、死を運命づけられてこの世に生まれてきた。しかし、その死を刑罰として受けとめるのではなく、永遠の解放として、安らぎの訪れとして受け入れることができるはずである。」といい、田沼靖一が「ヒトは、進化の過程で可老可死を選択することで生き残ることができた生物の末裔なのです。」という。こうして死が悲惨な運命ではなく、種の保存のための積極的な戦略であることは分かった。
しかし、連綿と続くヒトという種の中で、この私というものの存在はなんなのか? ドーキンスが言うように単に遺伝子を運ぶ舟に過ぎないのか? という根本的な疑問は依然として解決されていない。肉体が滅ぶのは仕方がない。死とともに、私を構成している分子や原子は、超新星の爆発で生じた元の原子に戻ってこの宇宙の構成要素となるはずだ。つかの間借りていた分子や原子を、元の持ち主に返すときが来るのは必然でもある。
しかしそのとき、私の「心、意識、魂、アイデンティティ、精神」というものはどうなるのだろうか。唯物論的に考えれば、エンゲルスの言うように、単に「意識はタンパク質の存在の仕方」でしかないのだから、赤いバラが枯れてしまえば「赤い」という存在の仕方も、バラという存在とともにすべてなくなってしまうと考えるべきだろう。
死んだら意識はどこへ行くのか
それならそれでも良いのだが、しかし、もっときちんと理解したい。つまり、意識はどこにあるのか。それはどのようにしてこの世界を認識できるのか、身体が死ぬと意識はどうなるのか、といったことをもっと深く知りたい、と思うのです。
ゴーギャンがその絵に秘めた問い「我々はどこから来たのか 我々は何ものか 我々はどこへ行くのか」の、「我々は何ものか?」を問うことは、古代ギリシャに始まる脳と心の関係についての根源的な考察であり、結論が簡単に出せるような問いではないことは十分に分かってるが、それでも問い続けないわけにはいきません。

意識は脳のなかの水分子が関係
現在の脳科学の定説によれば、脳に140億個あるニューロンのシナプス結合の強度の変化によって記憶が蓄えられるとしている。意識もこのニューロンの相互間の作用であるという考えが現在の主流です。こうした脳科学の主張にたいして、いくつかの新しい仮説がある。
酒を飲むと酔っぱらって気持ちが良くなる。酒癖の悪い人もいて、酔っぱらっていたときのことを覚えていないことがある。アルコールがどういう仕組みで”意識”を奪うのか、その機序は分かっていない。脳にはアルコールの受容体がないのである。
同じように、全身麻酔の機序も分かっていない。「脂肪溶解度説」が現在の麻酔学の定説であるが、これは脂肪に解けやすいものほど脳の中に入りやすい、脳の中に入りやすいほど麻酔効果が高いという比例関係を説明しているに過ぎない。
ポーリングがキセノンの全身麻酔に関する講演を聴いたとき、不活性ガスであるキセノンに麻酔効果があることに興味を持った。どんな物質とも化学反応を起こさないから「不活性」なのである。そのキセノンが、どのようにして脳に作用して意識を奪い、麻酔効果を生じるのか。
ポーリングが考えたのは、キセノンが水のクラスターを安定させて、小さな結晶のようなものを作るのではないか、ということだった。そして全身麻酔効果のあるすべての薬品が水のクラスター形成を安定化し、小さな結晶水和物を作り出すことを見つけた。水分子どうした互いにくっつきやすい状態を作ることが全身麻酔効果の分子機序であることを発見したのである。
ヒトのこころの原点である”意識”をとる全身麻酔の効果が水分子の振る舞いに依存しているのなら、”こころ”は脳の中の水分子が示す何らかの現象ではないかということになる。しかし、ポーリングの研究はこれ以上は進まなかった。
脳の渦理論
ポーリングの考え発展させ、複雑系の概念を導入して「脳の渦理論」を提唱しているのが中田力である。『脳のなかの水分子―意識が創られるとき』
水分子、ヒドロニウムイオン、水素イオン、水酸化物イオン、大小さまざまな水分子のクラスターが、それぞれの形態と役割とを常時変化させながら存在する水という物質は、全身麻酔薬によって作られる結晶水和物というもうひとつの構造を獲得することによって、意識を操作する現象を引き起こすと主張する。
脳は水を管理することでニューロンネットワークを保護する発泡スチロールのような緩衝材を作り上げ、同時に熱の流れを、大脳の機能素子として利用することに成功したのである。そこから”意識”が生まれた。
情報理論学的にいえば、大脳皮質はエントロピー空間を作っている。そして情報を扱う空間には等価のノイズが必要である。最大のエントロピーであるニューロンのランダムな発火があり、そのランダム性を下げることによって情報が意味を持ちうる。そして、物理学的にいえば、熱とは最もエントロピーの高いエネルギー形態である。熱は等価のノイズを大脳皮質全体につくりだす材料として都合がよい。熱放射の作り上げる大脳皮質全体の等価ノイズ、これが意識の根源であると、中田は主張する。
脳のグリア細胞、それの多く存在するアクアポリンと呼ばれる水分子の通路、グリア細胞のマトリックス構造による緩衝作用によって衝撃から守られている脳、マトリックス構造の中の、アクアポリンによる水分子移動によって乾いた空間となり、脳の冷却装置としての役割をする脳の形態が熱放射による等価ノイズを与え、脳が情報を受け入れる準備を整える「覚醒」した状態をつくりだしている。こうして脳の渦理論が完成する。
私のはしょった説明ではよく分からないかもしれない。松岡正剛がもっと良くまとめているので参照されたい。
意識が脳の中の水分子の活動に依存しているのなら、「私」が死んだら、脳の水分子の活動も終わるのであるから、「私」という意識はこの宇宙からは無くなる。
「私」を構成していた分子は、ばらばらになり、もとの宇宙の中に帰っていく。我々は超新星爆発の結果生じた分子を、つかの間借りてこの体と意識を構成しているだけの存在で有り、借りたものは返すだけのことと考えれば、「死」もまた宇宙の永遠の営みの中で生きることなのかもしれない。
「脳の渦理論」はNHKの番組「爆笑問題のニッポンの教養」でも放映されたらしい。トンデモ科学扱いをされたりもしている。あくまでも仮説である。


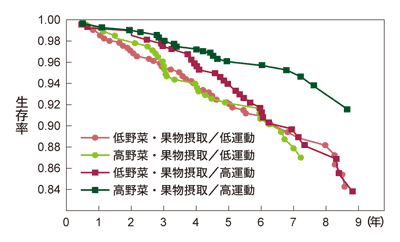






以前数回コメントやご相談をさせていただきました「まる」です。
木下さんと同じステージで膵尾部だったこともあり、このブログをよんで代替医療もやってきたつもりでしたが、再発です。12月にもご相談させていただきましたが、そのとき5mmだった肺の腫瘍が7/12に1cmの大きさの肺転移と確定し、他にも2~3mmのものがひとつあります。他の臓器への転移はありません。これって、普通のペースですか?速い?遅い?
7/24より、ジェムザールの点滴を開始しています。抗癌剤は、いったん効いたとしても完治は難しく、だんだん効かなくなり、すい臓がんに関しては、種類もそう多くなく、残っているのは副作用の強い薬になっていって、延命しか残っていないのかな、という感じです。(この前のブログにもしっかり書いてありました)
そこで、陽子線の治療を検討していますが、副作用として肋骨に近いので骨折の危険があること、肺炎を起こし悪化する危険があることなどを言われどうしようかと悩んでいます。その先生はオリゴメタは、めったにないと言われました。オリゴメタでないとしたら、1cmのものをつぶしてもあまり意味はないようにも思います。
このブログなどで新しい情報などもみてきて、すい臓がんでも3割はオリゴメタの可能性ありというのも見たように思います。その辺はどうでしょうか? それと抗癌剤ジェムザールを始めたばかりなので、この薬の効果をみての方がいいのかとなやみながらも、怖いのはそれを待っているとジェムザールの結果がでないで陽子線もできなくなることです。
すい臓がん治療は本当に博打ですね。
まこさん。
やはり再発でしたか。残念です。
しかし、膵臓がんの転移が肺だけで有り、その個数が10個以下ならオリゴメタの可能性も有り、予後は比較的良いです。
とはいっても、完治することまでは難しいでしょう。
https://satonorihiro.xyz/post-2242/
しかし転移した肺の腫瘍を積極的に手術することもあるようです。陽子線とどちらが良いのか、何とも申せませんが、手術なら保険適用ですね。
転移した時点で、積極的な治療はしないという選択肢もありますが、なかなか難しい選択です。
お返事ありがとうございます。あくまでも可能性でしょうが、それにかけてみようかな、という気持ちになってきました。手術は、負担が大きいのでしたくありません。陽子線でもつぶせるのは2個くらいまでだろうといわれました。1cmの腫瘍に対し、周囲1cmはつぶれるので直径3cmは肺がつぶれるといわれました。装置によってもっとピンポイントでやれたりするのでしょうか?